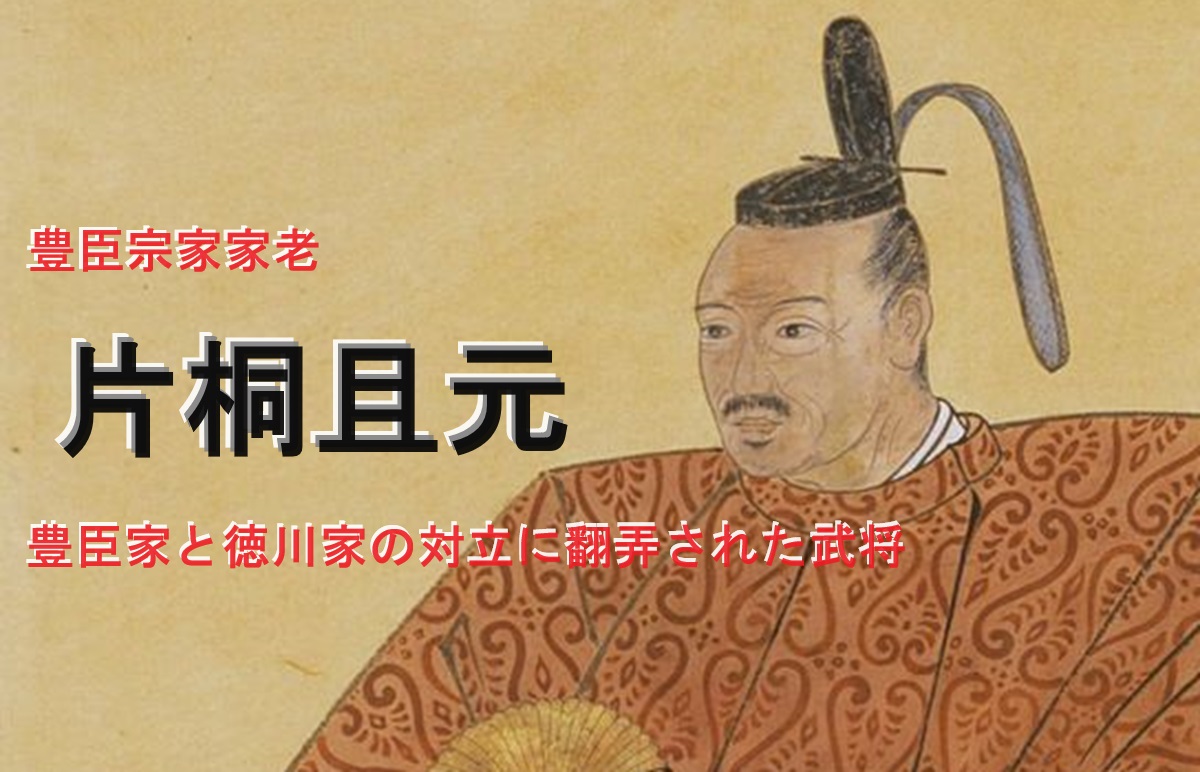護良親王(もりよししんのう)は、鎌倉幕府の討幕に多大な功績を挙げて建武の新政では征夷大将軍に補任された後醍醐天皇の第三皇子です。
幼くして仏門に入っていたのですが、鎌倉時代末期に還俗して討幕の兵を挙げ、畿内各地で幕府軍との戦いを繰り返し、最終的な勝利に大きな貢献をしました。
もっとも、その後、同じく鎌倉幕府討幕に貢献した足利尊氏と対立し、また後醍醐天皇との行き違いなどもあって建武政権下で失脚して鎌倉に幽閉された後、中先代の乱の混乱の中で、足利直義の命を受けた淵辺義博によって殺害されるという悲しい最期を迎えています。 “【護良親王】鎌倉幕府滅亡後の征夷大将軍” の続きを読む
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)