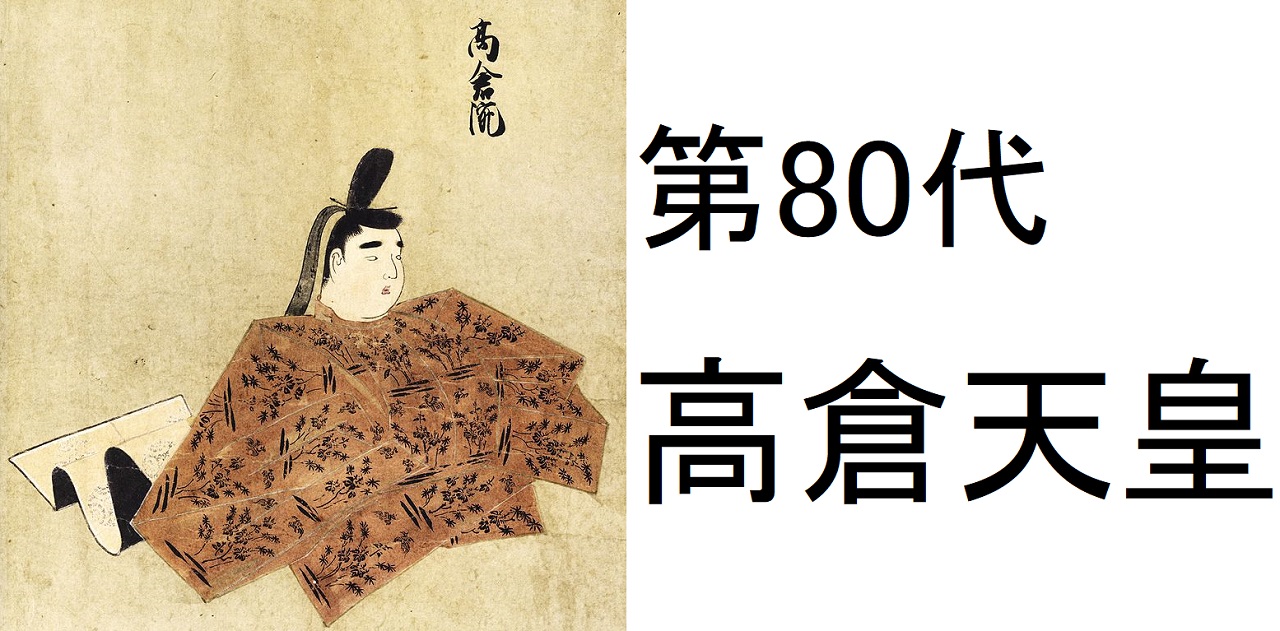岡田以蔵(おかだいぞう)は、天誅と称して幕末の京で幕府方の要人を斬りまくった土佐藩郷士です。
武市瑞山(半平太)の命に従い、多くの暗殺を行ったことから、同時期には「天誅の名人」と呼ばれ、後世では「人斬り以蔵」と称されて「幕末の四大人斬り」の1人にも数えられています。
もっとも、最後には兄貴分と慕う武市半平太に見捨てられ、同志たちにも軽蔑されながら斬首刑に処せられるという悲しい生涯を終えた人物でもあります。
本稿では、そんな悲しき人斬り・岡田以蔵の生涯について見ていきたいと思います。 “【岡田以蔵】武市半平太に従って天誅を繰り返した幕末四大人斬りの1人「人斬り以蔵」” の続きを読む
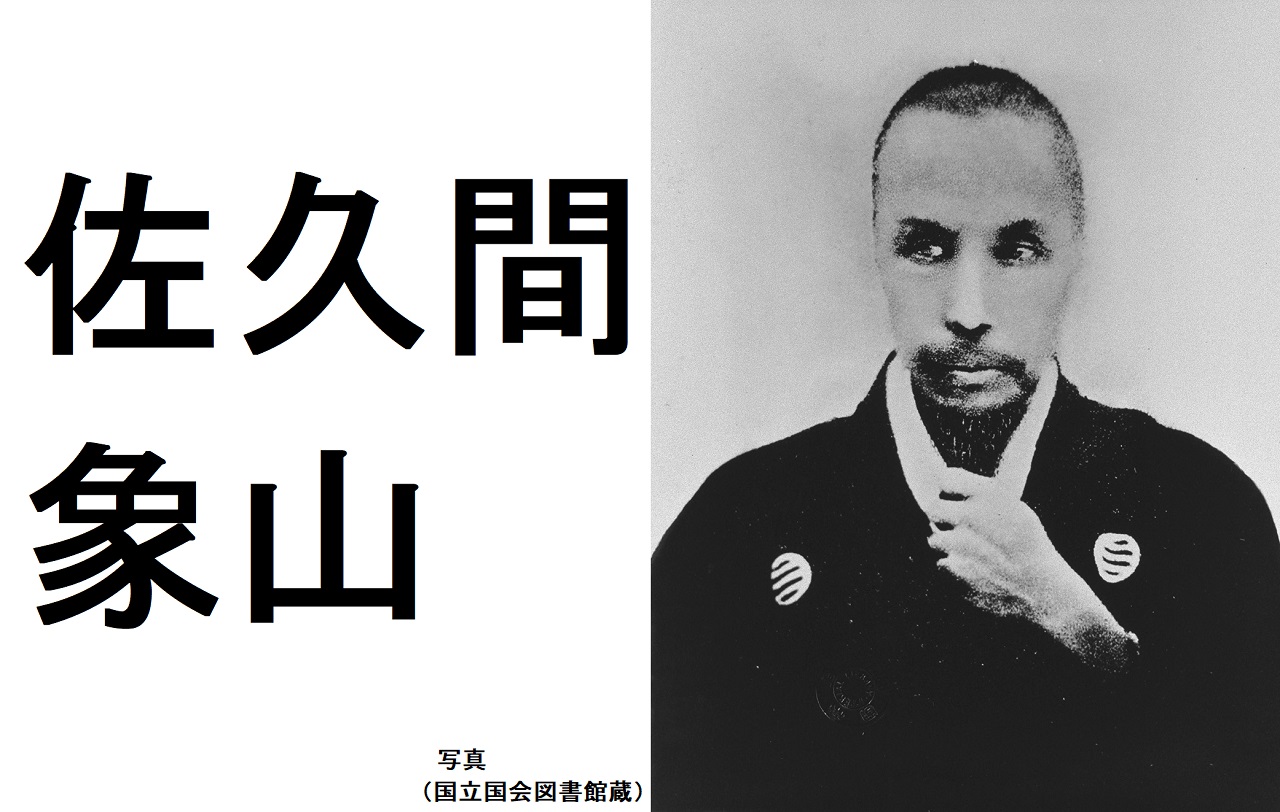




.jpg)
.jpg)