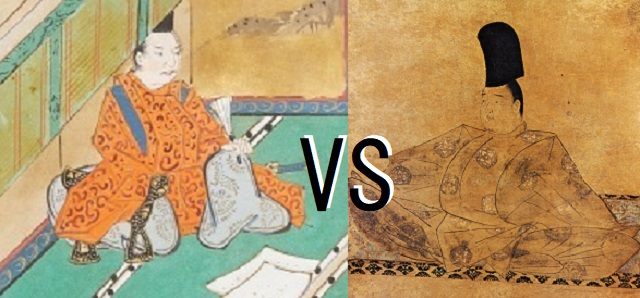崇徳天皇(すとくてんのう)は、鳥羽上皇の中宮であった藤原璋子(待賢門院)が、白河上皇との不貞行為の結果として産まれた複雑な血縁関係を持つ天皇です。
系図的には自分の子でありながら妻の不倫相手(白河上皇)の子であるということから、崇徳天皇は、系図上の父である鳥羽天皇から徹底的に嫌われて育ちます。
この環境は崇徳天皇が成長した後も変化はありませんでした。
この争いは、譲位して崇徳上皇となってからも続き、崇徳上皇と鳥羽上皇(及び後を継いだ後白河天皇)との争いは、朝廷を二分する大戦となった保元の乱を誘発しました。
保元の乱に敗れた崇徳上皇は、失意のうちに讃岐国に流され、同地において苦難を受け続けて死んだ恨みから怨霊となったとも言われています。
本稿では、苦難の歴史を歩んだ崇徳天皇の人生について見ていきたいと思います。 “【第75代・崇徳天皇】保元の乱に敗れて流され怨霊となった悲劇の帝” の続きを読む




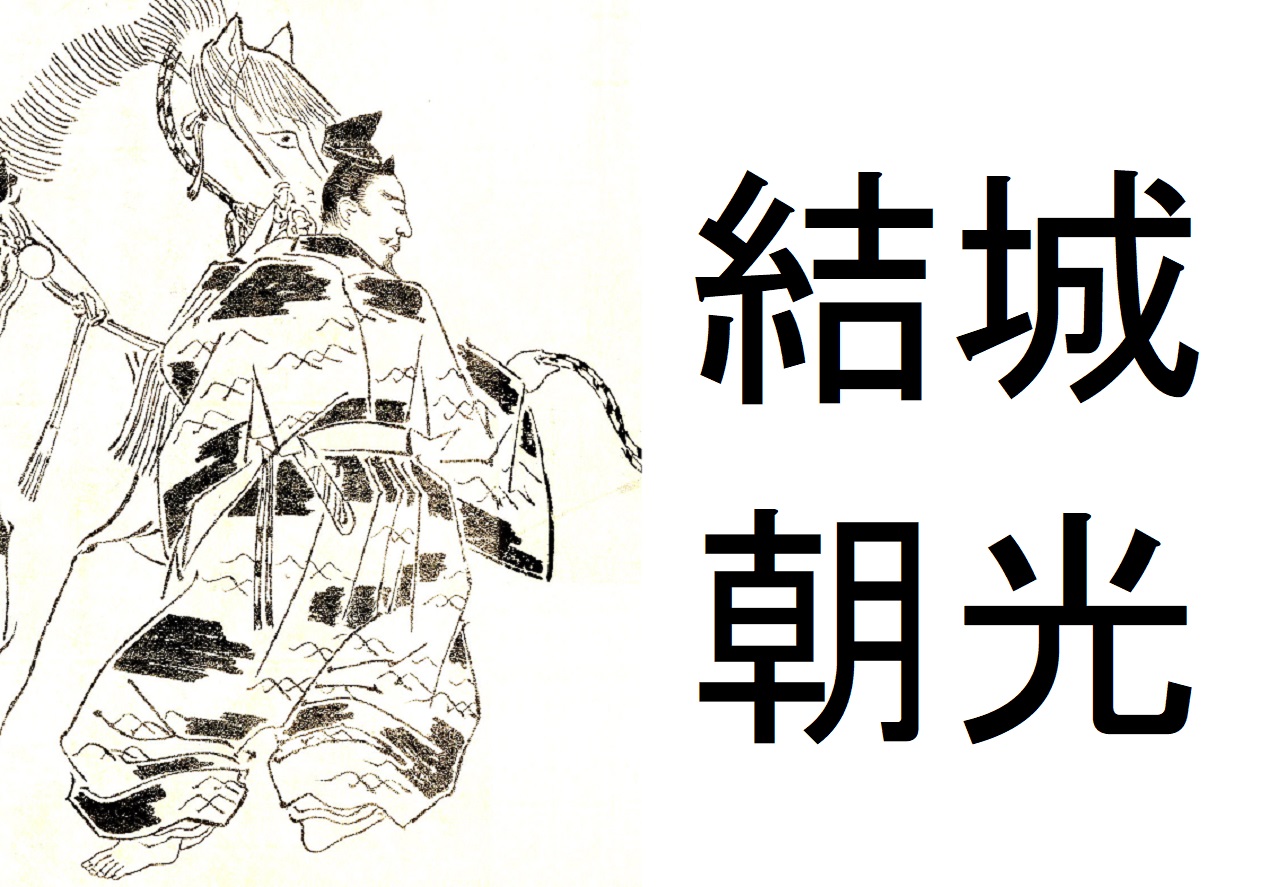
.jpg)