
宮古湾海戦は、箱館戦争における戦闘のひとつで、虎の子の軍艦であった開陽丸が座礁・沈没したことによって制海権を失った旧幕府軍が、制海権を取り戻すため、新政府軍の新鋭軍艦・甲鉄を奪取しようとして勃発した戦いです。
近代化していく西洋式の軍艦を、前近代的な敵船乗り込みとその後の敵船制圧により奪取しようとしたアボルダージュと呼ばれるいわゆる接舷攻撃戦という、極めて興味深い戦いです。
結果は、旧幕府軍の作戦失敗に終わりますが、とても珍しい戦いですので、本稿で概略を紹介したいと思います。 “【宮古湾海戦】旧幕府軍が制海権回復のため新政府軍の軍艦奪取を試みた戦い” の続きを読む
.jpg)



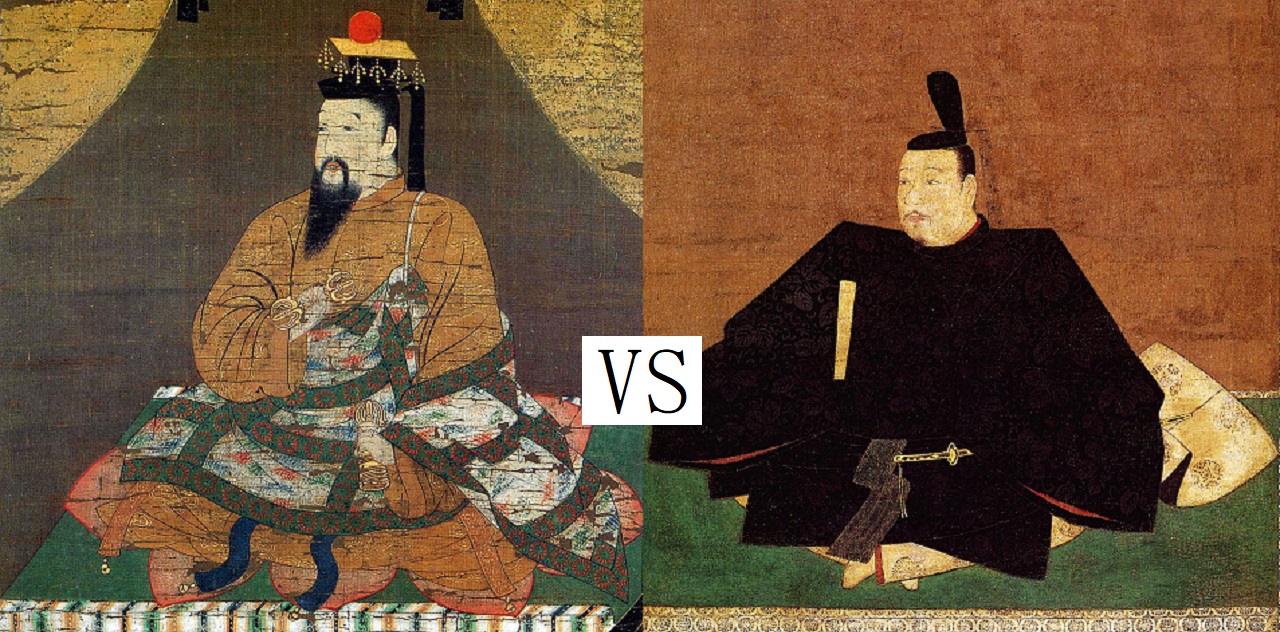
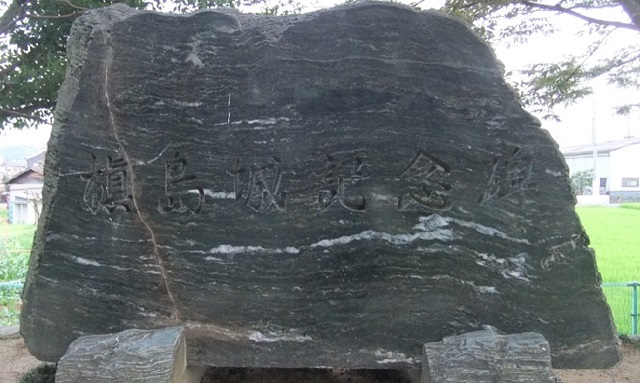
.jpg)
