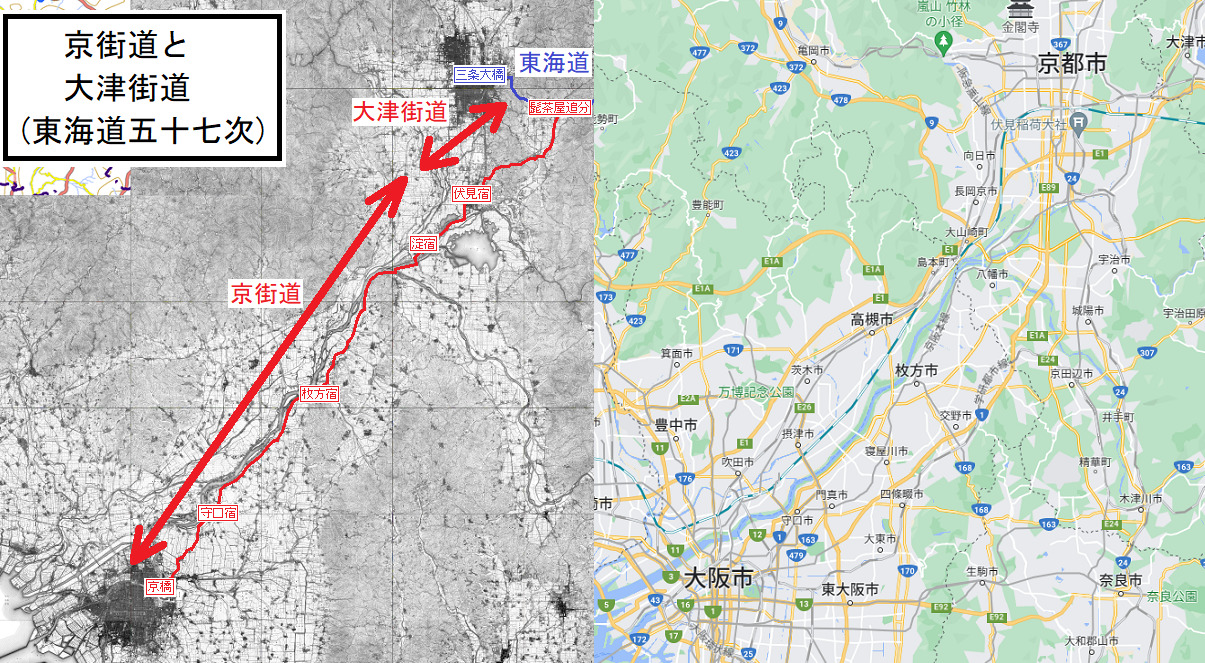百済寺(くだらでら・くだらじ)は、天平勝宝2年(750年)頃に百済王敬福によって建立されたと言われる河内国・交野郡中宮郷に存在した寺であり、現在でいうと大阪府枚方市内の淀川及び天野川沿いの小高い丘(交野ヶ原)上に位置します。
人質としてヤマト政権の下に送られた百済皇子が百済王氏の氏を与えられ、祖国滅亡後にヤマト政権下で力をつけて有力氏族となった後、その氏寺とするために建立した寺院でもあります。
ヤマト政権下で力を持った百済王氏は、百済寺の北部に一族を住まわせるための集落を形成していたとも考えられており、百済王氏の活躍の舞台として氏寺としてのみならずその周囲に広がった集落全体としての価値があります。
藤原摂関政治の確立により百済王氏が力を失ったために百済寺もまたいずれかの時点で失われてしまったのですが、その歴史的価値から昭和27年(1952年)3月29日に国の特別史跡に指定され、現在まで長い時間をかけて発掘調査が進められてきました。 “【河内百済寺】人質として日本に残された百済王族が大坂枚方に創建した氏寺跡” の続きを読む
.jpg)
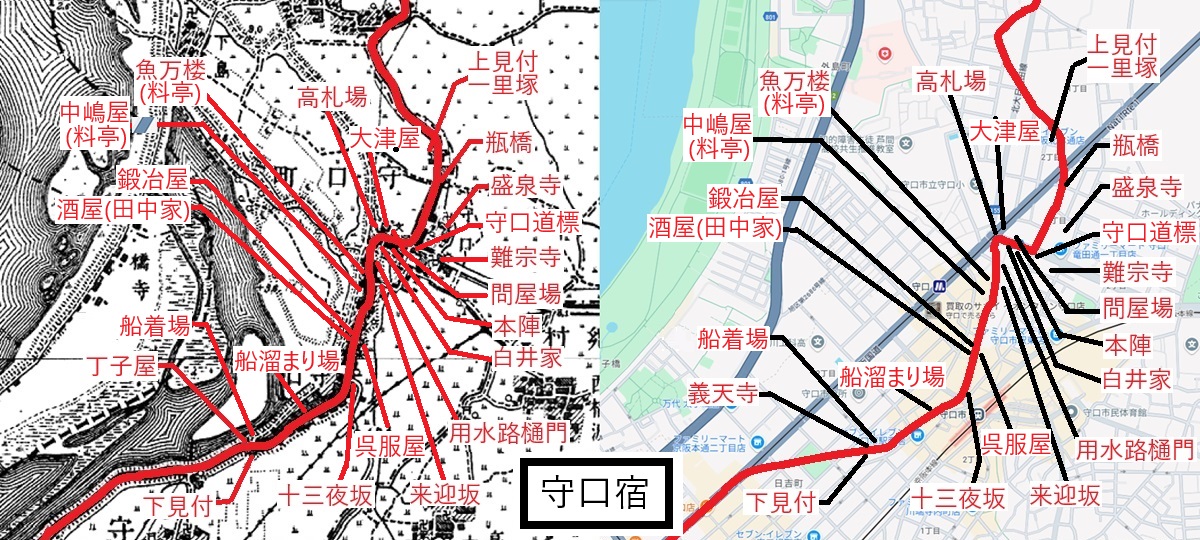
.jpg)
.jpg)
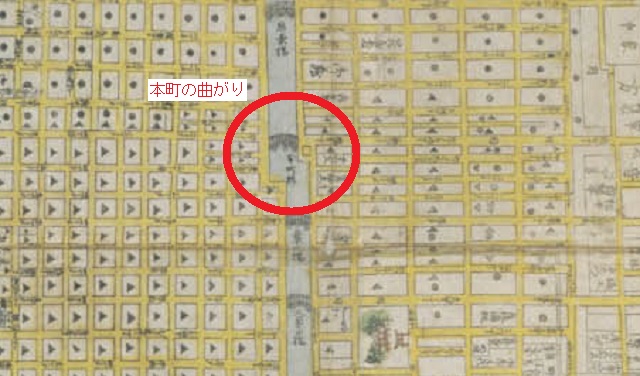
-1224x1200.jpg)
.jpg)
.jpg)