天下三戒壇とは、奈良時代に、日本中でたったの3寺にのみ設けられた僧侶が正式な戒律を授かるための施設である戒壇の総称です。
具体的には、東大寺(奈良市)、下野薬師寺(栃木県下野市)、観世音寺(福岡県太宰府市)に置かれた3つの戒壇の総称であり、本朝三戒壇とも言われます。
呪術的・統治的要素を重視した国家宗教として発展した日本の仏教では、出家者の悟りの境地などの側面が重要視されなかったために出家者の規律が軽視され、戒律や授戒の制度が発展しませんでした。
そのため、日本では僧侶資格があいまいとなっており、各種義務を免れる目的で僧侶を名乗る者(私度僧)が続出するようになりました。
この事態を苦慮した朝廷は、中国から鑑真を迎えて正式な授戒(受戒)制度を整え、厳格な僧侶資格制度を定めたのです。
その結果、奈良時代中期以降には、日本において僧侶となるためには授戒を経なければならないとされ、その授戒の場とされたのが天下三戒壇だったのです。 “【天下三戒壇】律令制度下における僧侶資格取得場所” の続きを読む
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
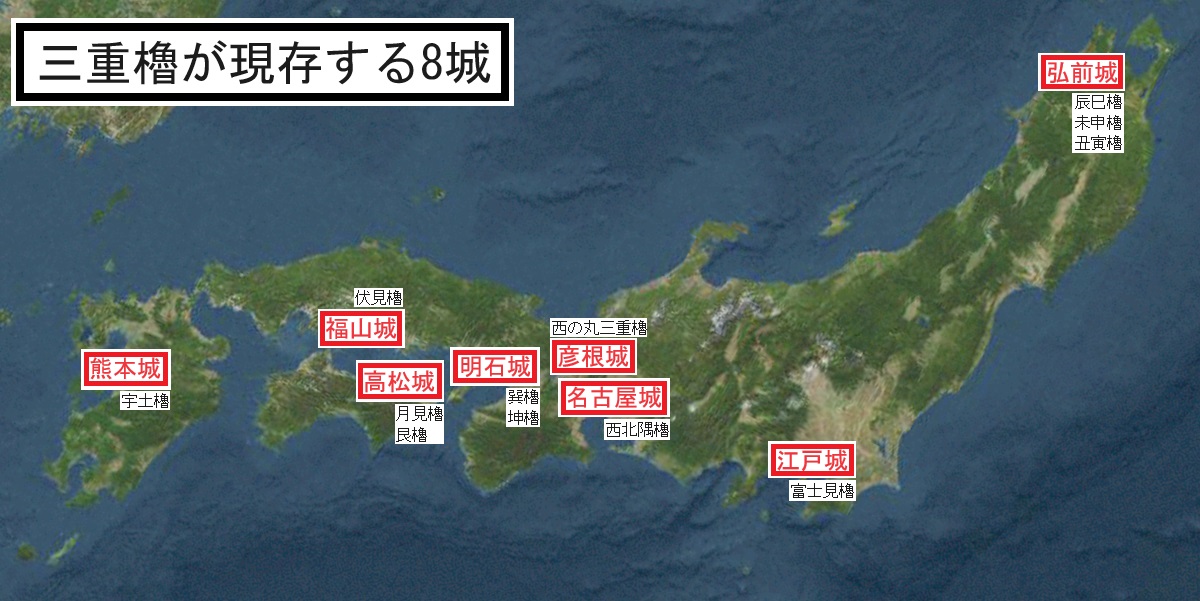
.jpg)
.jpg)