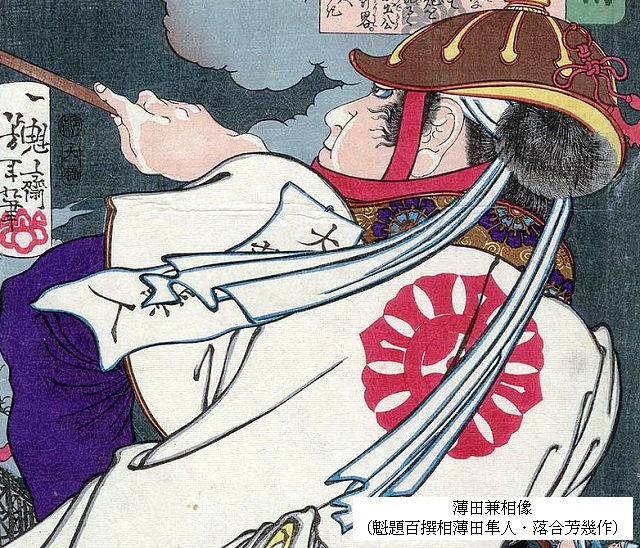京極高次(きょうごくたかつぐ)は、京極家と言うエリートの家に生まれながら、家臣筋に囲われた後、織田信長の下に人質として送られるという辛酸をなめながら育った人物です。
その後,負け組となる明智光秀や柴田勝家に与するという命の危機を乗り越え,妹・竜子や妻・初の後ろ盾もあって出世を重ね(そのため,女の尻によって出世したとして蛍大名と揶揄されます。)、大津城籠城戦の武功から遂には若狭国一国を得る大大名にまで成り上がり、若狭国小浜藩の初代藩主となります。
本稿では、そんな波乱万丈の人生を生きた京極高次の生涯について見ていきたいと思います。 “【京極高次】お家取り潰し危機から一発逆転し若狭小浜藩主となった蛍大名” の続きを読む





.jpg)