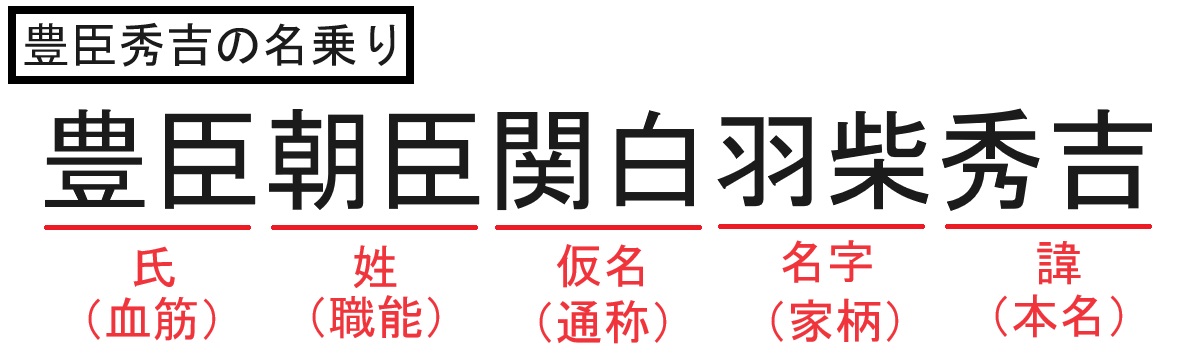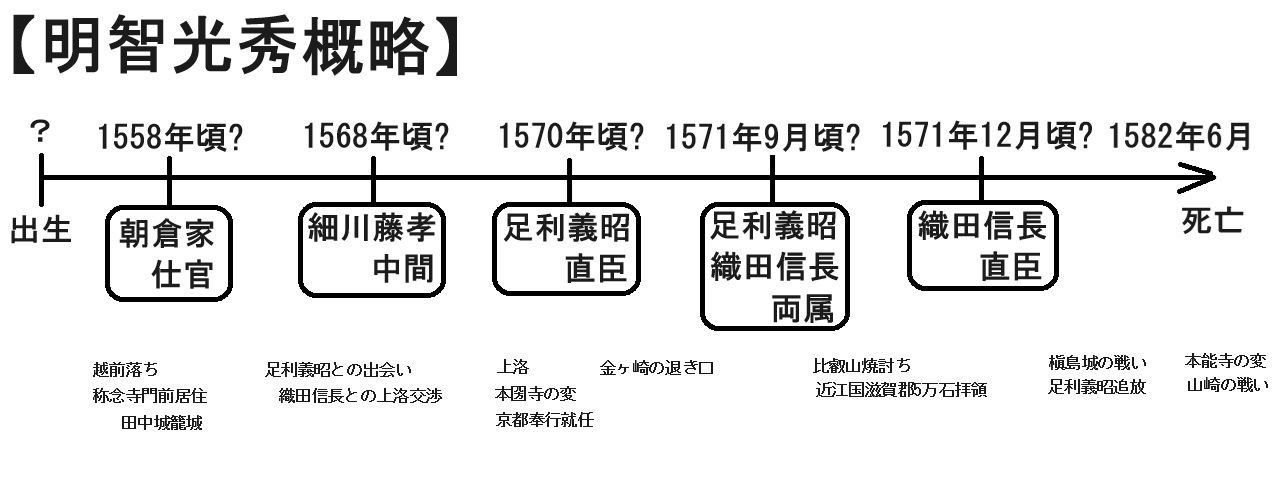中国国分(ちゅうごくくにわけ)は、天正11年(1583年)以降に羽柴秀吉と毛利家との間で行われた山陽道・山陰道における国境線の画定をいいます(広義ではそこで画定された国境線内の羽柴・毛利両陣営の具体的な領土配分も含みます)。
中国地方国境線については、天正10年(1582年)6月に備中高松城を包囲していた羽柴軍がその囲みを解く際に抽象的な取り決めをしたのですが、それを具体化するための交渉が必要でした。
そのため、天正11年(1583年)から具体的な領土配分(国境線画定)交渉が繰り返され、最終的に合意に至った結果が中国国分です。
中国国分の結果、毛利家・宇喜多家という西国巨大大名2家が羽柴秀吉に下ってこれを支える形となったこと、及びその後に羽柴領内で多くの家臣に領地が与えられたために羽柴秀吉の求心力が増大したことなどから羽柴政権(豊臣政権)確立の第一歩ともなった出来事でもありました。
本稿では、豊臣政権樹立のスタートともいえる中国国分について、その成立経緯から順に簡単に説明していきたいと思います。 “【中国国分】豊臣政権確立の第一歩となった中国地方の国境画定” の続きを読む
.jpg)
.jpg)
.jpg)