石山本願寺(いしやまほんがんじ)は、戦国時代に戦国大名に匹敵する勢力を誇った浄土真宗本願寺派が、摂津国東成郡生玉荘大坂(現在の大坂城所在地)に本山として構えた寺院です。
その前の拠点であった山科本願寺が法華一揆・六角連合軍に焼き払われて信仰の中心を失ったことへの反省から、本山の本願寺を中心として、堀と土塁で取り囲まれた寺内町で防衛し、さらにその外側に51もの支城を張り巡らせて防衛する城構え構造(城郭寺院)で成立しました。
その防衛力は強く、織田信長が10年の歳月をかけても攻め落とせなかった城としても有名です。
なお、当時は大坂本願寺と呼ばれており、江戸時代に入るまでに石山本願寺と呼ばれていた事実は確認できていないのですが、本稿では便宜上石山本願寺の名称で統一します。 “【石山本願寺(大坂本願寺)】戦国時代に一向宗本拠地となった城郭寺院” の続きを読む
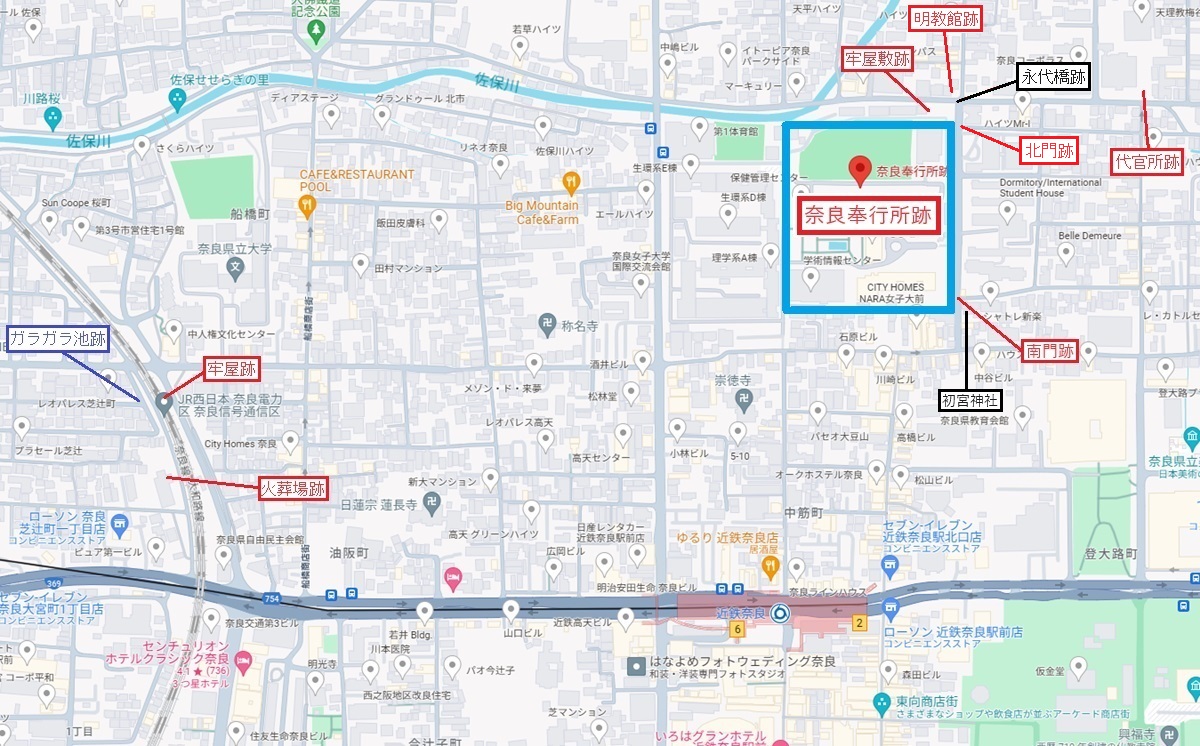


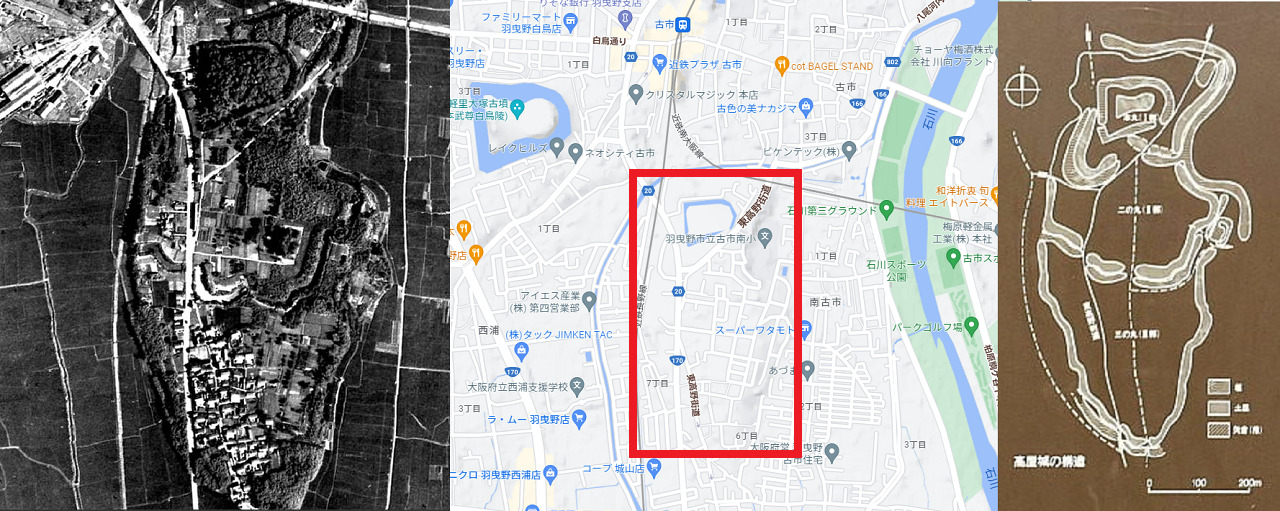


.jpg)


