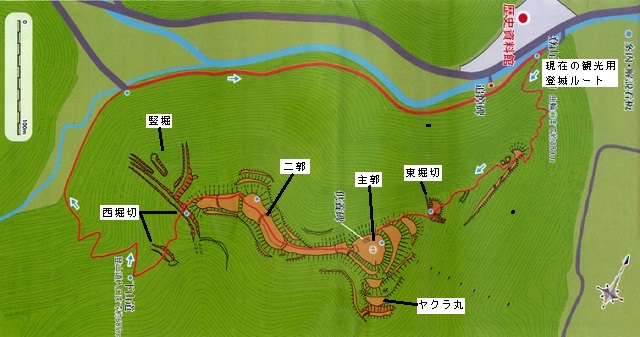近衛前久(近衞前久・このえさきひさ)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した公卿です。
関白宣下を受けた上藤氏長者となるなど朝廷内上り詰めたにも関わらず、上杉謙信や織田信長に接近するなどして武士の世界にも口を出して暗躍していきます。
特に織田信長とは鷹狩という共通の趣味から意気投合し、織田信長のために毛利攻めの後方支援や石山合戦の和議を取り付けるなど、外交面でその能力を発揮します。
もっとも、本能寺の変で織田信長が横死した後は豊臣秀吉に煙たがられて勢いを失っています。
本稿では、破天荒人生を歩んだ近衛前久の人生について説明死していきたいと思います。 “【近衛前久】全国を流浪した破天荒関白” の続きを読む
.jpg)