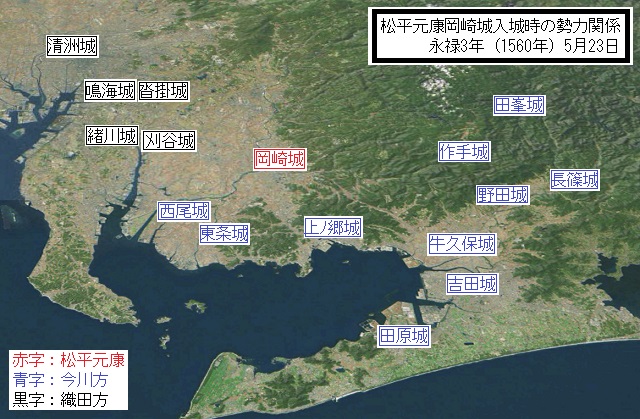第一次高天神城の戦い(だいいちじたかてんじんじょうのたたかい)は、天正2年(1574年)に、武田勝頼率いる武田軍が、徳川方の最東端拠点であった遠江国・高天神城を攻略した戦いです。
元亀3年(1572年)10月に始まった武田信玄の西上作戦によって領内が蹂躙された徳川家と、その後に武田信玄が死去したことにより家督相続での家内統制に苦慮した武田家との間で繰り広げられた一進一退の攻防戦の1つです。
戦術的に見ると、武田勝頼が大軍を動員して高天神城を攻撃したのに対し、後詰を出せなかった徳川家康・織田信長の威信を大きく下げるという結果をもたらしました。
他方で、戦略的に見ると、遠江国内に拠点を得てしまったがために、この後、高天神城を防衛するために相当の戦力を費やす必要が生じたため、武田家を大きく疲弊させる結果をもたらしています。
本稿は、このように後の武田・徳川・織田の勢力関係に大きな影響をもたらした戦いとなった第一次高天神城の戦いについて、そこに至る経緯から順に見ていきたいと思います。 “【第一次高天神城の戦い】武田勝頼と徳川家康との間の遠州争奪戦の初戦” の続きを読む

.jpg)
.jpg)


.jpg)