豊臣秀長(とよとみのひでなが) は、豊臣秀吉の弟です。なお、豊臣は氏であり、名字は羽柴ですので、正確な名乗りは「羽柴大納言豊臣朝臣秀長」となり、当時は苗字+諱で表すのが通常であることから、略すと「羽柴秀長」が正しいと思うのですが、本稿では便宜上、一般に用いられる「豊臣秀長」の表記で統一します。
豊臣秀長は、超ブラック体質の織田家の武将として全国を飛び回されていた豊臣秀吉の代理としてその代わりを務めることができた稀有な人物であり、短期間で異例の出世を遂げる豊臣秀吉の傍らにあって、後の軍事・政治面で天下統一事業に大きく貢献した人物です。
温厚な人柄によって家臣団や諸大名との調整役を務めるなど豊臣政権にとってなくてはならない立場にあり、大成した後の豊臣秀吉に異を唱えてその制動を制御できる唯一の人物でもありました。
武官としても優秀であり、中国攻めでは山陰方面攻略を、四国征伐では総大将を務めてこれらを成功させ、最終的には、大和国・紀伊国・和泉国と河内国の一部に及ぶ110万石を超える石高を領する大大名となり、また従二位権大納言となって大和大納言と尊称される出世を遂げています。 “【豊臣秀長】豊臣政権の潤滑油であった豊臣秀吉の弟” の続きを読む
.jpg)
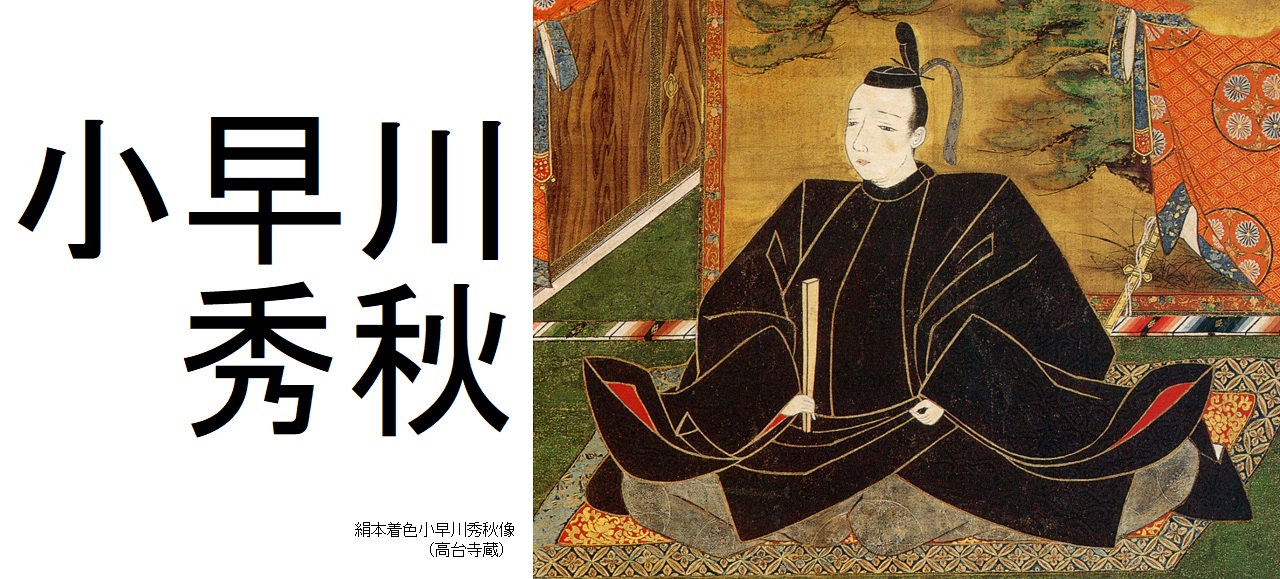
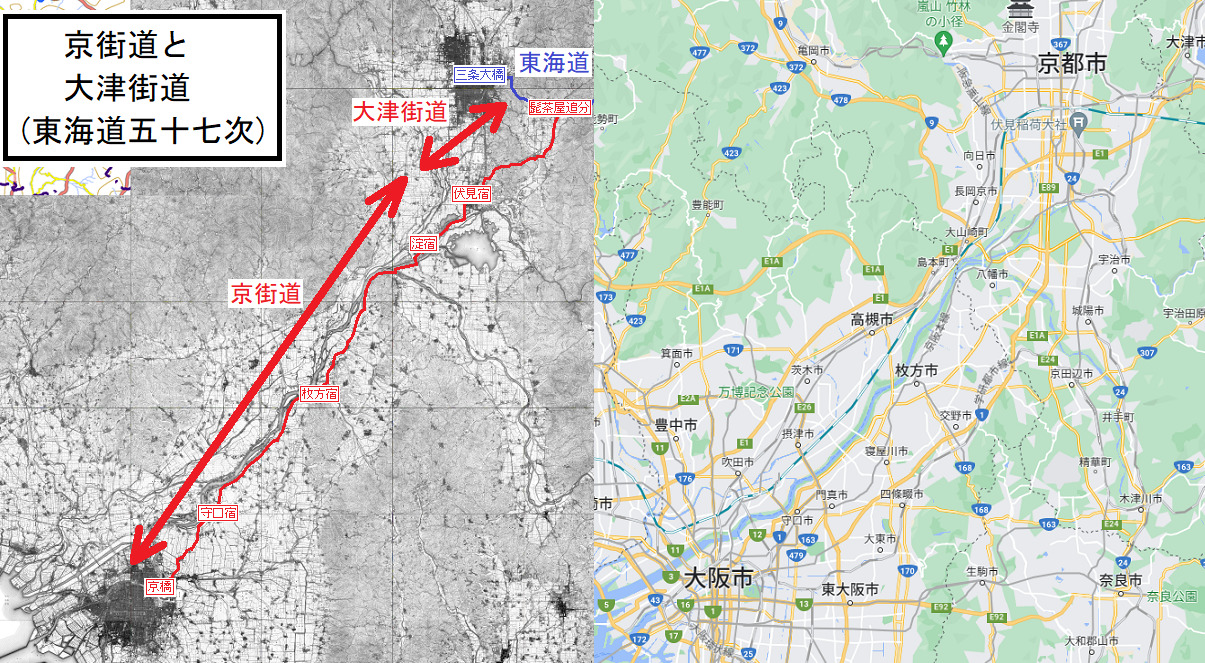
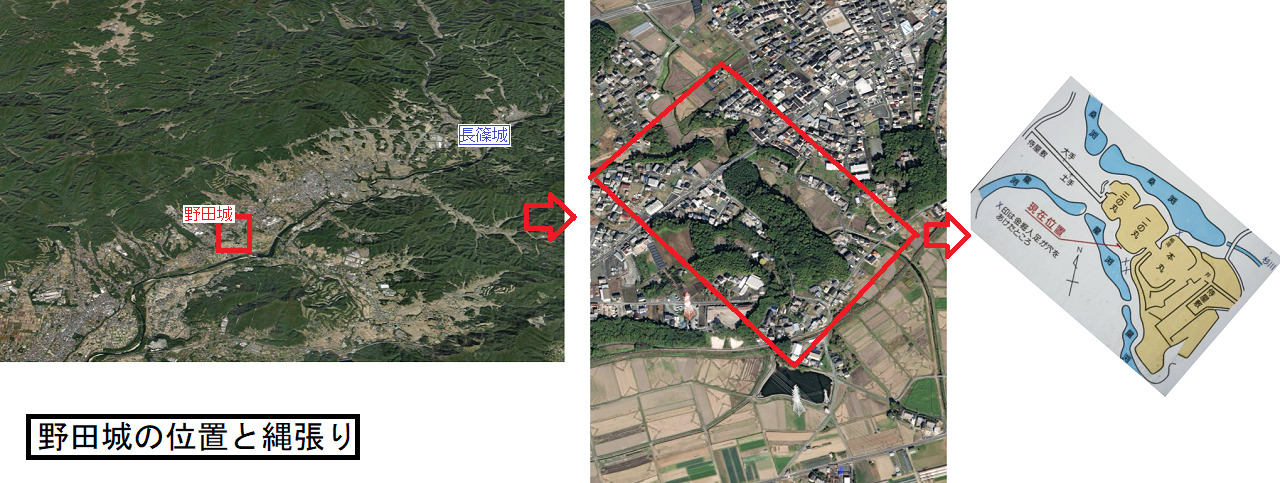
像.jpg)


縄張り.jpg)
