三国干渉(さんごくかんしょう)は、明治28年(1895年)4月23日、フランス・ドイツ帝国・ロシア帝国の列強三国が、日本に対して、6日前である同年4月17日に調印(国家代表者間による交渉・条約文作・署名による内容確定)された日清戦争の講和条約である下関条約(批准は同年5月8日)の内容うちの1つである日本による遼東半島所有を放棄して清に返還するよう求めた勧告です。
日本側としては、日清戦争において多くの損害を被りながら獲得した遼東半島を失うことに抵抗が多かったのですが、当時の日本陸海軍に列強三国を相手にして戦うだけの国力はなく、やむを得ずに勧告に従って遼東半島を返還するという決断に至っています。
この点については、日本政府のみならず日本国民全体が悲憤慷慨し、この屈辱を忘れないために「臥薪嘗胆」をスローガンとして、国力増強・軍事力増強に努めていくようになりました。 “【三国干渉】臥薪嘗胆を合言葉にロシアを仮想敵国にするに至った国辱事件” の続きを読む

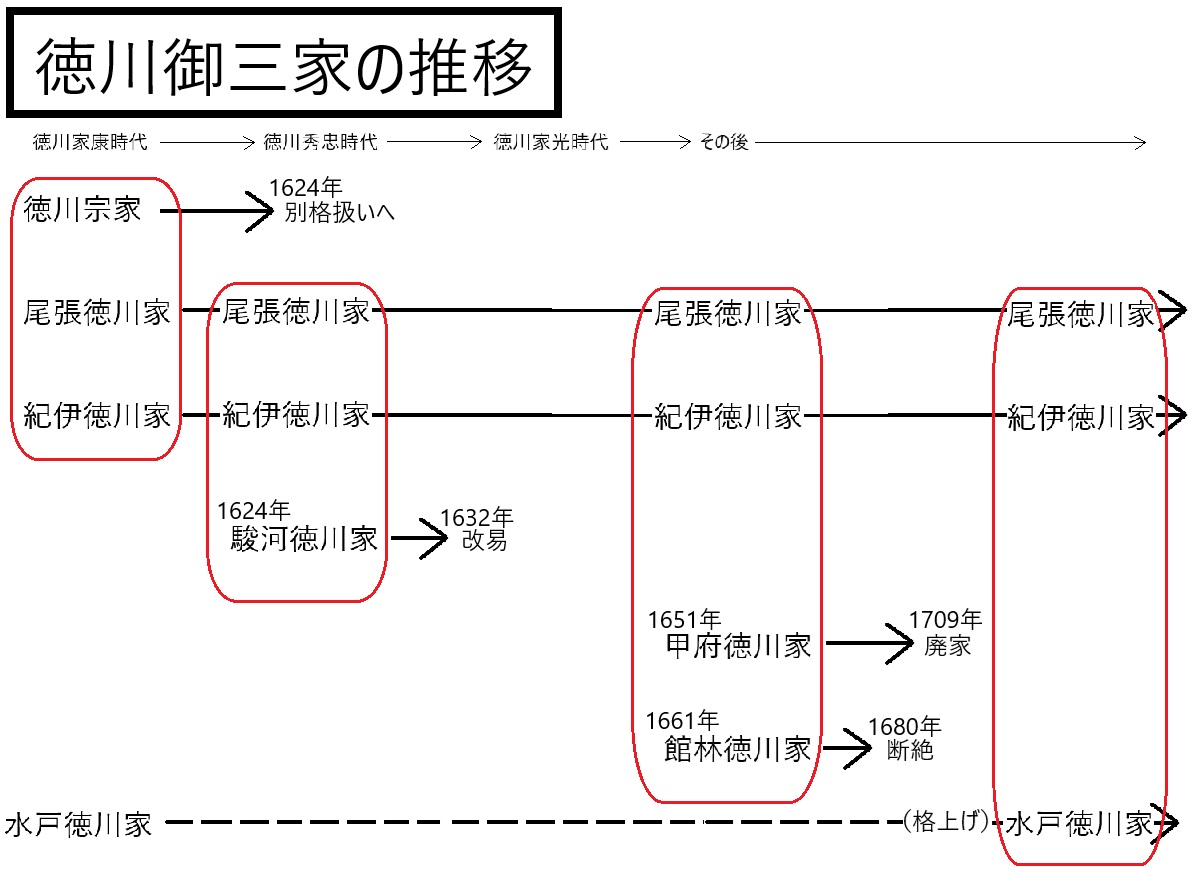
.jpg)
.jpg)

