御三卿(ごさんきょう)は、江戸時代中期の第8代将軍・徳川吉宗と、第9代将軍・徳川家重の子によって創設された徳川将軍家の一門家です。
紀伊徳川家出身の徳川吉宗が、ライバルである尾張徳川家の影響力を低下させるために創設されたと考えられており、徳川宗武(徳川吉宗三男)を家祖とする田安徳川家、徳川宗尹(徳川吉宗四男)を家祖とする一橋徳川家、徳川重好(徳川家重次男)を家祖とする清水徳川家がこれに該当します。
御三家に次ぐ高い家格を持つとしながらも当初は大名として藩を形成することも政治権力を持つこともなく、将軍の親族でありながら将軍家の部屋住みとして扱われ、将軍家や親藩大名家に後継者がない場合に養子を提供することを主な役割とするに過ぎない家でした。
もっとも、幕末期には幕政にも関与するようになり、江戸幕府最後の将軍である第15代将軍・徳川慶喜が一橋家から輩出されたことでも知られています。 “【御三卿】紀伊徳川系で徳川将軍家を承継する目的で創設された分家” の続きを読む

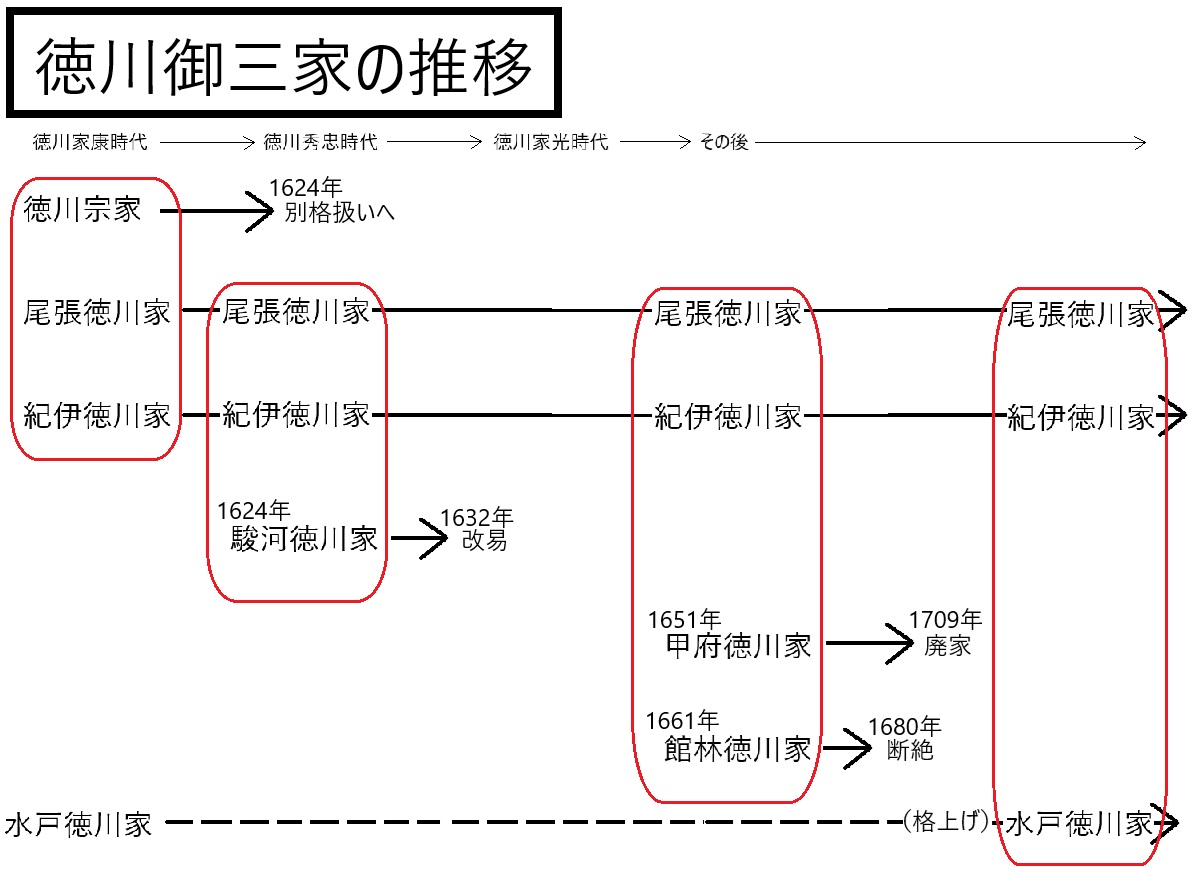
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)