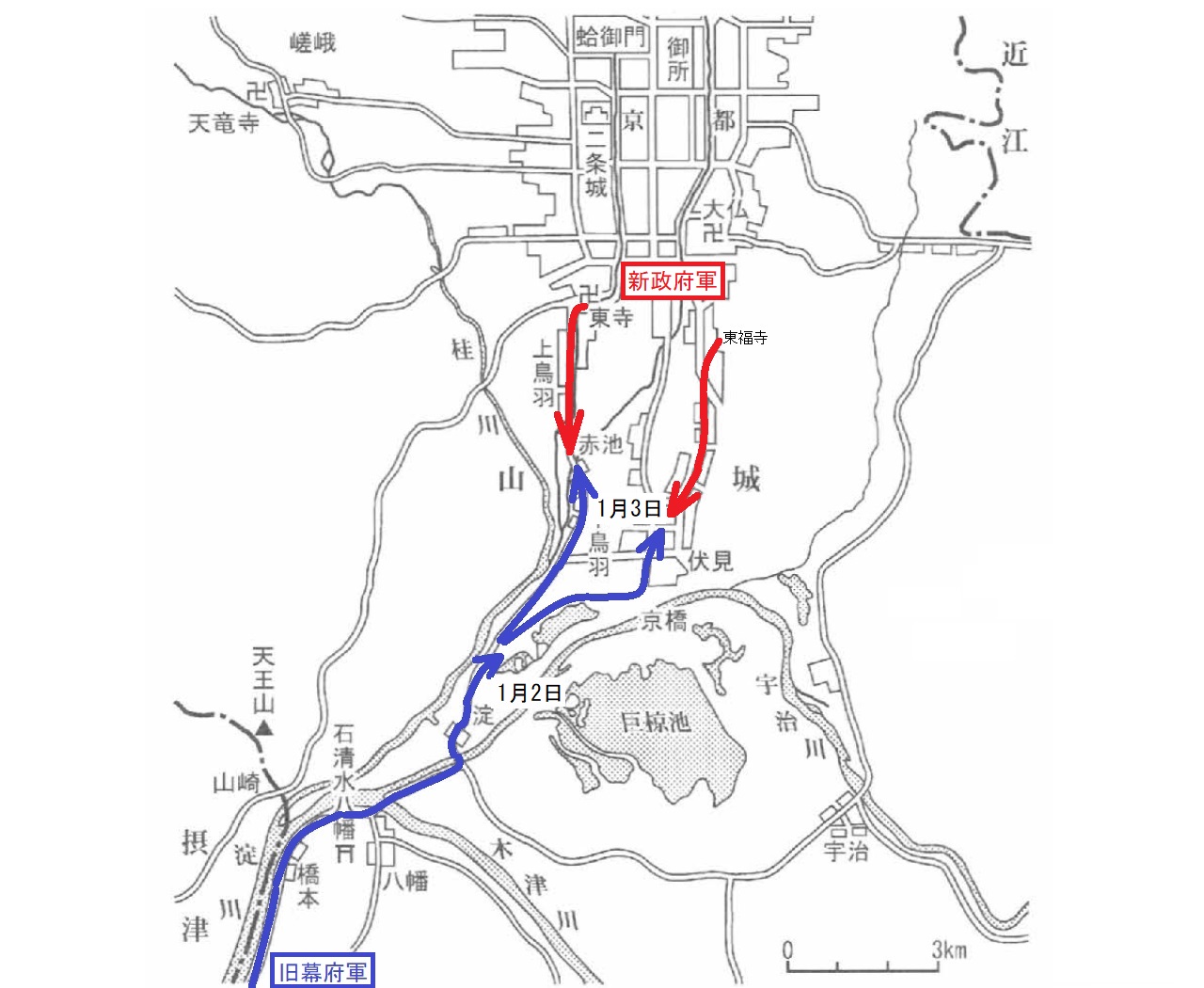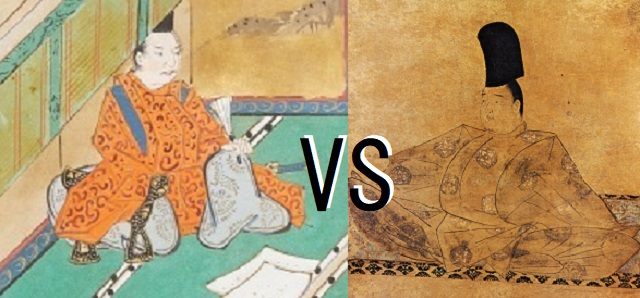小牧・長久手の戦い(こまき・ながくてのたたかい)は、天正12年(1584年)3月から11月にかけて、織田家家臣団を吸収して勢力を拡大する羽柴秀吉と、これに対して織田家当主として争った織田信雄とこれに同調した徳川家康とが戦った一連の合戦です。
この戦いは、羽柴軍が、織田信雄の本拠地であった尾張国に攻め込む形で行われたため、尾張国を中心としておこなわれたのですが、反羽柴方において秀吉包囲網が形成されたことから、全国に波及し、連動した戦いが北陸・四国・関東など全国各地で行われています “【小牧・長久手の戦い】もう1つの天下分け目の合戦” の続きを読む