日本の近代司法制度の生みの親が誰かご存知ですか。
維新の十傑とも言われ、日本の近代司法制度を作り上げるという偉大な功績を残したにもかかわらず、意外に知名度の低い人物・江藤新平です。
知っている方は、日本史通の方か法曹関係者の方ではないでしょうか。
知名度の低さは、逆賊の汚名を着せられて処刑されたこともその原因となっています。
本稿では、そんなマイナーな偉人・江藤新平の生涯について見ていきたいと思います。
【目次(タップ可)】
江藤新平の出自
出生(1834年3月18日)
江藤新平は、天保5年(1834年)3月18日、肥前国佐賀郡八戸村(現在の佐賀県佐賀市八戸)で、佐賀藩の下級藩士であった江藤胤光とその妻・浅子の長男として生まれます。幼名は恒太郎・又蔵といいました。
なお、父の江藤胤光は「手明鑓」という低い身分の武士であったとされています。
藩校・弘道館に入学(1848年)

佐賀藩士の息子である江藤新平は、嘉永元年(1848年)、佐賀藩の藩校である弘道館へ入学します。
江藤新平は、頭脳明晰であり、入学後の内生(初等中等)課程は成績優秀者として学費の一部を官給されたほどだったそうです。
ところが、この頃に父・江藤胤光が職務怠慢の咎により郡目付役を解職されて永蟄居の処分となったため、たちまち江藤新平らの生活は困窮します。
そのため、江藤新平は、弘道館の外生課程に進学できませんでした。
そこで、江藤新平は、儒学・国学者でもあった枝吉神陽(副島種臣の兄)の私塾にて学ぶようになります。
そして、江藤新平は、ここで師・枝吉神陽から思想的な影響を受け、嘉永3年(1850年)に枝吉神陽が「義祭同盟」を結成すると、大隈重信・副島種臣・大木喬任・島義勇らとともにこれに参加します。
佐賀藩での活躍
成長した江藤新平は、佐賀藩の政治に参画するのですが、その能力の高さから次第に藩で重用されていくようになります。
そして、江藤新平は、23歳となった安政3年(1856年)、開国・富国強兵・人民重視の必要性を理路整然と説く意見書「図海策」を発表します。
そして、この頃から、尊王思想への傾倒が顕著になり、その思想はやがて討幕へと向かっていきます。
明治維新
脱藩し蟄居を命じられる(1862年)
討幕思想に傾倒していった江藤新平は、文久2年(1862年)、ついに脱藩し京に向かいます。
そして、京で維新志士として活動を開始した江藤新平は、長州藩士の桂小五郎(木戸孝允)や公家の姉小路公知らと交流し、人脈を築いた後、2ヶ月ほどで帰藩します。
このころの脱藩は重罪であったため、通常は死罪となるはずであったのですが、その才を惜しんだ前藩主・鍋島直正の直截裁断により江藤新平は、永蟄居(無期謹慎)とされます。
この謹慎により、江藤新平は、寺子屋を開きながら、同士との密かな交流や幕府による長州征伐(幕長戦争)での出兵問題では鍋島直正への献言を行うなど政治的活動を続けます。
明治新政府に参加(1868年)
その後、慶応3年(1867年)の大政奉還によって江戸幕府が消滅したこともあり、江藤新平は、同年12月に謹慎が解かれて郡目付として佐賀藩政(洋式砲術、貿易関係の役職)に復帰します。
このとき、江藤新平は、岩倉具視に対し、大木喬任(後の東京府知事)と連名で江戸を東京と改称すべきこと(東京奠都)を献言し、慶応3年(1868年)7月17日、江藤新平の献言が通って江戸は東京と改称されます。
そして、慶応4年(1868年)9月、元号が明治に改められ、明治元年10月13日に明治天皇が東京行幸により東京に入り、慶応3年(1868年)12月9日の政復古の大号令により明治新政府が誕生します。
戊辰戦争(1868年)
その後、幕臣と明治新政府との間で戊辰戦争が勃発すると、江藤新平は東征大総督府軍監に任命され、土佐藩士の小笠原唯八とともに江戸へ偵察に向かいます。

江藤新平が江戸にいた際、薩摩藩の西郷隆盛と幕臣の勝海舟との会談で江戸城無血開城が決定します。
そして、慶応4年(1868年)4月11日、幕臣・山岡鉄舟ら立ち会いの下で江戸城の引き渡しがなされたのですが、この江戸城引き渡しののどさくさに紛れて、江藤新平は江戸城内に残された江戸幕府の政務に関する文書・帳簿類を悉く接収します。
これはそれまでの幕府による政治状態を把握し、その後の明治新政府の政治に生かすための先を見据えた実務家ならではの極めて重要な行為です。
何の情報もない状態でゼロから統治機構など作れるはずがありません。
倒幕をゴールと見る血気にはやるだけの維新志士とは目の付け所も能力も違います。

その後、上野で旧幕臣らを中心とする彰義隊が活動し始めたと聞くと、大村益次郎らとともに討伐を主張し、軍監として上野戦争で戦い彰義隊勢を寛永寺周辺に追い詰めた上、佐賀藩のアームストロング砲を遠方射撃する戦術などにより彰義隊を瓦解させます。
岩倉使節団不在の留守政府で法制度を整備
明治新政府で活躍(1868年10月)
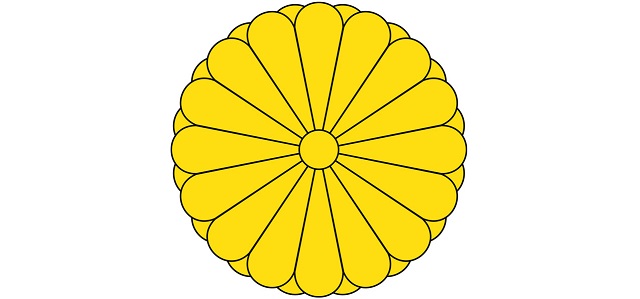
能力の高さを買われた江藤新平は、明治新政府に徴士(新政府が能力を買って新たに登用した者)として登用され、政治体制変化に伴って発生する諸問題の対応にあたることとなります。
正式に明治新政府の一員となった江藤新平は、明治元年(1868年)10月20日、会計官(後の大蔵省)判事(長官下の6人の判事の1人)に任命され、会計・財政などを担当し、「政府急務十五条」を記すなどして財政健全化に尽力します。
その後、明治2年(1869年)、佐賀藩主・鍋嶋直正が藩政改革のため帰郷することとなり、江藤新平・副島建臣らもそれに従って佐賀藩に戻ります。
佐賀藩に戻った江藤新平は、明治3年(1870年)1月、大参事(準家老)に就任し、副島種臣と共に藩政改革に着手します(「佐賀の七賢人」の1人にも数えられます。)。
もっとも、江藤新平は、その能力を買った明治新政府高官から再度呼び戻され、中央政治に復帰し、賞典禄100石を賜るとともに太政官中弁に任命されます。
明治政府の初期国家統治制度の問題点
明治新政府は、江戸幕府が締結した不平等条約の改正が至上命題として成立しています。
そのため、欧米列強と交渉するためには、前提として、それまでの特権階級による私刑的な法制を廃し、近代的な法制度を整備することが不可欠でした。
ところが、明治新政府の国家機構は、国家の意思を左右大臣・大納言・参議で構成される三職会議で決定し、これを具現化する立法・行政・司法の三権を太政官が統括するというシステムになっていました。
そして、太政官の下、司法権は刑事裁判権・司法行政権を所管する刑部省、民事裁判権を所管する民部省、訴追権を有する弾正台に分掌されていました(また、地方においては、藩府県の地方官が司法権を掌握していました。)。
このシステムは太政官が裁判制度の最終決裁権を持つことになりますので、政治が裁判に介入するという致命的な欠陥を持っていました。
この難題にメスを入れ、近代的な法制度の確立を目指したのが江藤新平でした。
江藤新平は、「政治制度上申案箇条」を提出して三権分立(特に司法の独立)の重要性を説き、明治3年(1870年)10月、日本最初の私擬憲法となる「国法会議案、附国法私議」を起草します。
また、江藤新平は、明治4年(1871年)2月には制度取調専務として国家機構の整備に従事し、大納言・岩倉具視に対して30項目の答申書を提出します。
岩倉使節団不在の留守政府で活躍
.jpg)
その後、明治4年(1871年)11月12日、岩倉具視を全権とする政府首脳の重鎮達や留学生を含む総勢107名が、視察のためにアメリカ合衆国、ヨーロッパ諸国に派遣されます(岩倉使節団)。
岩倉使節団のメンバーは、明治新政府の最重鎮ばかりでしたので、その出発に際し、残されたメンバー(西郷隆盛・板垣退助・大隈重信・江藤新平ら)との間で、使節団が戻るまで日本での重要な政策決定や重大な人事異動を行わないとの合意がなされていました。
簡単に言うと、お偉いさんの一部がしばらくいなくなるけど、残された者だけで勝手なことをするなと釘を刺されていたということです。
ところが、残ったいわゆる留守政府では、岩倉使節団が不在となった直後から、これ幸いと、全国の戸籍の作成、太陽暦の採用、電信、学制、徴兵制など様々な政策を実行し、四民平等政策を行うなど、抜本的改革を次々と施行していきます。
そして、この留守政府の中で、江藤新平は、近代司法制度の制定を担当します(この江藤新平らによる鬼の居ぬ間の改革が、後に帰国した大久保利通らとの対立を生みます。)。
近代裁判制度・裁判所設立(1871年)
江藤新平は、法律を整備し・裁判を執行するための機関として司法省を設立し、それまでのお上の独断で一方的に処断されるという意識の庶民に、人権により守られるという概念を植え付けようと努力します。

そして、明治4年(1871年)には、裁判所が作られ、法律による統治の撤退を目指します。
民法典編纂事業(1871年頃〜)
明治維新の前、江戸幕府の時代に、国内法の統一と、不平等条約改正を目的として、法典編纂の試みが始まっていました。
江戸幕府は、慶応3年(1867年)2月、パリ万国博覧会に徳川昭武、箕作麟祥らを派遣したのですが、このときに迅速な裁判を目にした外国奉行の栗本鋤雲によって、日本への導入が検討されます(もっとも、相続法については、単独相続制が日本の現状に適すると考えており、フランス法をそのまま導入するのは反対であったとされています。)。
そして、この事業は、明治新政府にも引き継がれます。

明治新政府になった後は、江戸幕府時代から続ける箕作麟祥に、江藤新平が加わって民法典編纂事業が続けられます。
そして、江藤新平は、明治六年の政変により下野するまでの間に、明治4年頃の制度局『民法決議』(明治4年・1871年ころ)、司法省明法寮『皇国民法仮規則』(明治5年・1872年ころ)、司法省『民法仮法則』(明治6年・1873年3月)と次々に民法草案を発表していきます。
もっとも、江藤新平の民法典編纂事業は、拙速と批判され、その後の司法省の編纂と各種論争の調整などの紆余曲折もあって民法典の完成は、明治29年まで待つこととなります。
警察制度整備
また、江藤新平は、警察制度についても大改革を行います。
これは、犯罪捜査についても同様で、有名なところで言うと、明治5年(1872年)には、犯罪容疑者(被疑者)を確保するため、指名手配の制度を確立し、実効性を上げるためにそこに顔写真を添付したりしています。
初代司法卿就任(1872年4月25日)

江藤新平は、司法省が設置されると明治5年(1872年)4月25日、初代司法卿(現在の法務大臣・最高裁判所長官・国家公安委員長に相当)に任命されます。
このとき江藤新平は、司法にたずさわる者の心得として「司法省誓約」を記し、法律の遵守と人民の権利保護を謳っています。
この後、江藤新平は、明治5年(1872年)10月2日、人権問題を高めるため、遊女の人身売買の規制を目的とした太政官布告(通称:芸娼妓解放令、明治5年10月2日太政官布告第295号)、同年10月9日、前借金で縛られた年季奉公人である遊女たちは妓楼から解放する「前借金無効の司法省達」(明治5年司法省達第22号)などを次々発布していきます。
行政訴訟の道を作る(1872年11月28日)
また、江藤新平は、明治5年(1872年)11月28日、「司法省達四十六号」を定め、役人の行為により人民の権利が侵害された場合にその是正を裁判所に提訴できると定めます。
これは、日本で初めてお上の判断に異議を唱えることができる画期的なものでした。
日本初の行政訴訟法の制定です。
実際、この法律に基づき、京都の大商人・小野組が、京都府参事・槇村正直を訴えるという事件が起こります。
参議就任(1873年)
その後も、江藤新平は、文部大輔、左院副議長、参議と数々の役職を歴任し、その間に学制の基礎固め・四民平等・警察制度整備など近代化政策を推進します。
留守政府内の不興
江藤新平は、官吏の汚職に厳しく、新政府で大きな力を持っていた長州閥の山縣有朋が関わったとされる山城屋事件、井上馨が関わったとされる尾去沢銅山事件らを激しく追及し、予算を巡る対立も絡み2人を一時的に辞職に追い込みます。
これらは、今では当たり前の行為かも知れませんが、司法権の形成過程の当時であれば画期的といえる行為であり、そのため周囲の不興を買った面は否めません。
また、江藤新平は、急速な裁判所網の整備を行ったために明治新政府の財政的な負担が追いつかず、大蔵省の井上馨との確執を招いたりもしています。
留守政府構成員と岩倉使節団構成員の対立
岩倉使節団帰国(1873年9月13日)
明治留守政府の重鎮として次々と司法制度を確立させていった江藤新平ですが、この偉業を妨害する事情が発生します。
明治新政府の真の実力者の集団である岩倉使節団が、明治6年(1873年)9月13日帰国したのです。
岩倉使節団は、日本を離れている間は留守政府が重要な政策決定や人事登用をしないとの約定で訪欧していたのですが、日本に戻って留守を預かっていた留守政府が次々と政治システムを構築していたこと、江藤新平が参議に就任していたことに驚きます。
そして、岩倉使節団の面面は、留守政府が掴もうとしていた明治新政府内での権限を取り戻そうとして、行動を開始します。
明治六年の政変(1873年10月23日)

帰国した岩倉使節団らの面々は内治優先の考えを持ち、留守政府のメンバーである江藤新平の参議からの罷免を求めたりし、新たな政治システム構築を始めます。
このように留守政府組と岩倉使節団組とが次々と対立していきます。
また、朝鮮出兵を巡る征韓論問題でも両者の意見は対立し、この意見対立から発展した政変により、最終的に明治天皇の英断により政争に敗れた西郷隆盛は政府の役職を辞め、軍人・官僚合せて約600人が政府を去ります。
江藤新平下野する(1873年10月24日)
そして、江藤新平もまた、西郷隆盛に従って、板垣退助・後藤象二郎・副島種臣と共に辞表を提出して参議を辞職し、明治6年(1873年) 10月24日下野します。
西郷隆盛らの下野により政敵を排除した大久保利通は、明治6年11月、内務省を設立し、警察、国土交通、地方行政などを掌握し、それまでの留守政府の政策を一変させ、国を挙げての富国強兵と殖産興業を推し進めます。
佐賀の乱
江藤新平佐賀帰郷(1874年1月13日)
一方で税は重くなり、政府に不満を持つ士族や農民も出てきます。
また、このころの佐賀では、征韓論を奉じる反政府的な「征韓党」と、封建主事への回帰を目指す保守反動的な「憂国党」が結成されるなどの不安定な情勢から明治新政府からマークされていました。
政府を去った江藤新平は、明治7年(1874年)1月10日、愛国公党を結成し、また同年1月12日、民撰議院設立建白書に署名した上で、不平士族をなだめるために佐賀への帰郷を決意します。
これに対し,江藤新平の帰郷は、太政官より発せられた「前参議は東京に滞在すべし」との御用滞在の命令に反するものとして江藤新平を処断するための大久保利通の術策に嵌るものであるとして大隈重信・板垣退助・後藤象二郎らが江藤新平の東京慰留の説得をします。
ところが、江藤新平は、慰留の声を無視し、同年1月13日に船便で九州へ向かってしまいます。
江藤新平が東京を離れたとの知らせを聞いた大久保利通は、これを好機と見て、同日、佐賀討伐のための総帥として宮中に参内した上、同年2月5日には佐賀追討令を受けます。
なお、東京を発った江藤新平は、すぐには佐賀へ入らず、同年2月2日長崎の深堀に入った後にしばらく様子を見て、同年2月11日佐賀に入ります。
反乱軍の首領となる(1874年2月12日)
明治7年(1874年)2月9日、佐賀に於ける軍事・行政・司法の三権全権の委任を受けていた内務卿の大久保利通が、兵権を握る権限を得ており、嘉彰親王(後の小松宮彰仁親王)が征討総督として現地に着任するまですべての軍事行動事項を決裁し、佐賀鎮圧命令を下します。
明治新政府との衝突を回避するため、不平士族をなだめようと佐賀に戻った江藤新平ですが、明治7年(1874年)2月12日、憂国党の島義勇と会談を行い、逆に佐賀征韓党首領として擁立されてしまいます。
ここで、政治的主張の全く異なるこの征韓党と憂国党が共同して明治新政府に対する反乱を計画するに至ります。
佐賀の乱勃発(1874年2月16日)

そして、ついに明治7年(1874年)2月16日夜、憂国党が武装蜂起し士族反乱である佐賀の乱(佐賀戦争)が勃発します。
佐賀軍は県庁として使用されていた佐賀城に駐留する岩村高俊の率いる熊本鎮台部隊半大隊を攻撃、その約半数に損害を与えて遁走させた。
詳しい戦闘内容は割愛しますが、結論的には、激戦の末佐賀士族軍は、明治新政府軍に敗退し、江藤新平もは征韓党を解散して逃亡します。
そして、江藤新平は、同年3月1日に鹿児島鰻温泉の福村市左衛門方で湯治中の西郷隆盛に面会して薩摩士族の旗揚げ
を請うも断られます。
そこで、江藤新平は、続いて飫肥の小倉処平の救けで高知へ行き、同年3月25日、高知の林有造・片岡健吉のもとを訪ね武装蜂起を説くも、いずれも断られます。
後がなくなった江藤新平は、岩倉具視へ直接意見陳述を企図して上京を試みます。
江藤新平捕縛(1874年3月27日)

ところが、江藤新平は、京へ向かおうとしたした途上で、明治7年(1874年)3月27日、現在の高知県安芸郡東洋町甲浦付近で捕縛されます。佐賀へ送還される。
皮肉なことに、江藤新平が捕縛された理由は、江藤新平の手配写真が出回っていたためなのですが、この写真手配制度は江藤自身が明治5年(1872年)に確立したもので、まさかの制度制定者の江藤新平本人が被適用者第1号となってしまいました。
江藤新平の最期
私刑による死刑(1874年4月13日)
捕縛された江藤新平は、明治7年(1874年)4月8日、急設された佐賀裁判所で司法省時代の部下であった河野敏鎌によって裁かれることとなりました。
江藤新平は、法律を無視した私刑により、同年4月13日に河野敏鎌により除族された上、賊名を着せられて梟首の刑を申し渡されます。
判決言い渡しの際、江藤新平は、「裁判長、私は」と言って反論しようとして立ち上がろうとしたが、それを止めようとした刑吏に縄を引かれ転び、この姿に対して「気が動転し腰を抜かした」と悪意ある解釈まで受ています。
そして、その日の夕方に嘉瀬刑場において江藤新平の処刑が執行されました。
日本における司法制度を確立しようとした偉人の悲しすぎる最後です。享年40歳でした。
なお、この裁判については、大久保利通が金千円で河野敏鎌を買収して江藤新平を葬ったなどという風評が立っています。真偽は不明ですが、江藤新平が処刑された日の大久保利通の日記には、江藤新平ら12人が処刑され大安心などと記載していますので(大久保利通日記)、あながち嘘ではなかったのかもしれません。
晒し首
その後、江藤の首は嘉瀬川から4km離れた千人塚でさらし首にされました。
このときの江藤新平の首の写真は、インターネット上にも多数アップされていますので簡単にみることができますが、見たくない人もいると思いますので、本稿に引用することは控えておきます。興味がある人は自分で検索して見て下さい。
その後
その後、江藤新平の偉業の再評価がなされ、15年ほど経過した明治22年(1889年)に大日本帝国憲法に伴う大赦令公布により江藤新平の賊名が解かれます。
そして、大正5年(1916年)4月11日、正四位の官職まで与えられ、その名誉の回復がなされるに至ります。
