蜂須賀小六(正勝)は、豊臣秀吉の天下統一に貢献したその筆頭宿老です。
何度も主君を失った後、織田家の美濃国侵攻戦の際に豊臣秀吉の与力となり、その後直臣となってその覇業を支えました。
豊臣家筆頭宿老となり、最終的には蜂須賀家に阿波一国を与えられたことにより阿波徳島藩蜂須賀家の藩祖とされています。
なお、江戸時代に書かれた物語により野盗の頭目であったとか、墨俣一夜城の築城に貢献したなどというフィクションのイメージが作り上げられたため、ドラマなどでは面白おかしく描かれることの多い人物でもあります。 “【蜂須賀小六正勝】初期豊臣政権の筆頭宿老” の続きを読む
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
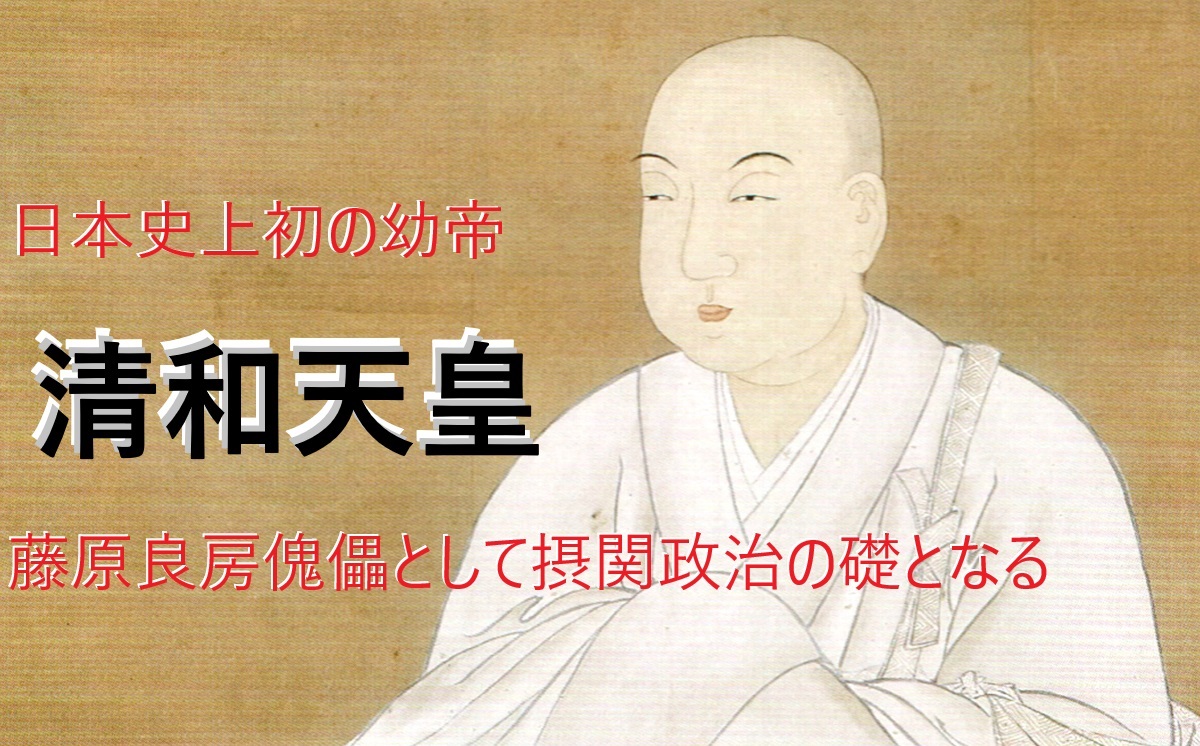
.jpg)
.jpg)