日本の近代化が始まった明治維新以降、日本政府は、欧米列強諸国に追いつき追い越すために各種の富国強兵政策を進めていきます。
そして、その一環として近代貨幣制度の整備を始め、明治4年(1871年)に造幣局(創設当時の名称は「造幣寮」)を創設し、硬貨の鋳造に取り掛かります。
その後、日本では各種硬貨が発行されていったのですが、欧米列強諸国に追いつくため、海外との貿易で利を得るため、海外植民地政策を進めるため、長引く戦争により資源が乏しくなっていったためなど、その時代を反映した興味深い造りとなっています。
そこで、本稿では、明治維新以降に日本において発行された(造幣局で鋳造された)近代・現代貨幣について、その歴史と発行硬貨の一覧を紹介していきたいと思います。
なお、記載内容は、本稿を書いた令和7年4月時点のものとなっています。
【目次(タップ可)】
明治政府による貨幣制度の整備
新たな貨幣制度の模索(1868年)
明治維新によって明治新政府が樹立されると、貨幣に関する政策も明治新政府が行うようになります。
もっとも、発足当初の明治新政府には、貨幣制度を整備する余裕はなかったため、明治新政府は江戸時代の文・朱・分・両という貨幣単位を継続利用し、また江戸時代の金貨・銀貨・銭貨や藩札などをそのまま通用させました。
その後、欧米先進国に対抗できる国を作るために富国強兵・殖産興業(近代産業育成)の政策を進めた明治政府は、近代的な統一的貨幣制度の確立を目指し、それまでの貨幣鋳造所であった金座・銀座を貨幣司に統合します(また、藩札処分令によって藩札を廃止します。)。
その上で、戊辰戦争に際して支出した多額の戦費を賄い、かつ殖産興業の資金に充てるため、明治新政府は、慶応4年(1868年)5月15日、参与兼会計事務掛三岡八郎(後の由利公正)の建議によって通用期限を13年間との期限を決めて通貨単位を両・分・朱のまま、旧来の藩札を踏襲した政府発行の太政官札を発行します。また、翌明治2年(1869年)には、太政官札を補完するものとして民部省札も発行されています。
もっとも、その印刷技術の未熟さから太政官札の偽札が大流行し、明治5年(1872年)4月にドイツの印刷会社に発注して発行された新紙幣である明治通宝と交換する形で回収されていきました。
造幣局創設(1871年)
また、明治政府は、近代硬貨の鋳造を目指して明治元年(1868年)にイギリス帝国・香港造幣局の造幣機械を購入した上で大阪の地に造幣局の建築を開始し、明治4年(1871年)に造幣局(創設当時の名称は「造幣寮」)を創設し、硬貨の鋳造に取り掛かります。
なお、新たに鋳造されることとなった硬貨については、明治2年(1869年) 7月、明治政府が、皇室御用として明治天皇の太刀飾りを担当していた当時最高の金工師・加納夏雄に対して新貨幣の原型作成を依頼し、同人が試鋳貨幣の作成をしたものです。
当初は、加納夏雄のデザインを基にイギリスに極印作成を依頼する予定だったのですが、加納夏雄作成の見本を見たイギリス人技師ウォートルスがその完成度の高さを高く評価し、これほどの名工が居るのにわざわざイギリスに依頼する必要はないと述べたことから、新貨幣についてのデザインから型の制作までが加納夏雄とその門下生に委ねられることとなりました。
円の誕生(1871年)
明治政府は明治4年(1871年)5月10日に新貨条例を施行して、以下の内容を採用しました。
①貨幣単位を従来の4進法を基準とした「両・分・朱」から10進法を基準とする「円・銭・厘」に変更(旧1両→新1円、1円=100銭=1000厘)
②旧貨幣は漸次廃止
③本位貨幣を金貨とし、1円金貨を原貨とする(金本位制)
④1円金貨の含有金を純金1.5g(23.15ゲレイン=1アメリカドル)とする
この新貨条例では、本位金貨(20円・10円・5円・2円・1円)、貿易銀(1円)、定位補助銀貨(50銭・20銭・10銭・5銭)、補助銅貨(1銭・半銭・1厘)の新貨が定められ、近代洋式製法によるこれらの金・銀・銅による新硬貨の発行がなされることとなりました。
また、この当時、世界ではイギリスから広まった国際的な金本位制が普及していたため、明治政府が新貨条例を制定するに際して金本位制が採用され、アメリカ・ドルの1ドル金貨に相当する1円金貨を原貨とする本位貨幣が定められ、兌換制度の確立を目指して、「大蔵省兌換証券」・「明治通宝札」を相次いで発行します。
また、国際的に流通していた洋銀(貿易銀)であるメキシコの8レアル銀貨(メキシコドル)をモデルとして貿易専用銀貨としての1円銀貨も発行されたのですが、本位金貨の絶対数不足のために貿易銀も本位貨幣扱いとされたため、新貨条例は金本位制をとりつつも、事実上は金銀複本位制となりました。
近代硬貨の歴史と各硬貨の説明
新貨条令による旧貨発行(1871年)
加納夏雄によって完成に至った日本初の近代硬貨の図柄は、表には菊紋・桐紋・日章・菊枝と桐枝・錦の御旗(日月旗)・八稜鏡が、・裏には登り龍が刻まれたものでした(なお、造幣局では製造過程での作業上の便宜のために年号=年銘が刻まれている側を裏、その反対側を表としています。)。なお、このときに欧州諸君主国の例に倣い硬貨の表面に天皇の肖像を刻むことが検討されたのですが、貴人に拝謁するための身分資格を厳格に問う伝統のあった日本では天皇の肖像を刻むことは不敬であると判断され、肖像の代わりに天子を表す龍図と日本のシンボルである旭日が刻まれることとなりました。
そして、この図柄は、当初発行された全ての硬貨に採用され(龍図の下に金額が刻印されてはいたものの、その他のレイアウトは同一でした)、価値の違いは材質と大きさによって区別されることとなりました。なお、余談ですが、金貨・銀貨の龍は阿、銅貨の龍は吽を表しており、2つで阿吽を構成しているという意味では微妙な違いがありました。
なお、明治15年(1882年)には、日本の中央銀行となる日本銀行が設立されています。
また、明治18年(1885年)には、日本銀行兌換銀券が発行され、銀本位制を確立するに至っています。
(1)旧金貨(1870年〜1897年)
① 旧20円金貨(1871年~1880年)

旧20円金貨は、直径35.06mm、33.33g、金900・銅100の硬貨であり、明治4年(1871年)に発行された新貨条例による本位金貨です。
なお、発行前年の明治3年(1870年)から鋳造が始められましたので、発行前年の同年の刻印が入ったものが存在しています。
発行年度の銘が存在するものは、明治3年・明治9年・明治10年・明治13年・明治25年のみであり、明治3年銘以外のものは新しい極印と鋳造機の試験もプルーフ硬貨の試作として鋳造されたと考えられており、また明治25年のものはシカゴ博覧会用の2枚しか鋳造されませんでした。
後に、明治30年(1897年)に貨幣法が制定されると、額面の2倍である40円として通用され、昭和63年(1988年)3月末に貨幣法が廃止されて通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律が施行されたことにより廃止とされました。
② 旧10円金貨(1871年~1880年)

旧10円金貨は、直径29.42mm、16.66g、金900・銅100の硬貨であり、明治4年(1871年)に発行された新貨条例による本位金貨です。
発行年度の銘が存在するものは、明治4年・明治9年・明治10年・明治13年のみであり、明治4発行のものに比べてその他のものは若干の縮小がなされています。
③ 旧5円金貨(1870年~1871年)

旧5円金貨は、直径23.84mm、8.33g、金900・銅100の硬貨であり、明治3年(1870年)に発行された新貨条例による本位金貨です。
④ 旧5円金貨・縮小(1872年~1897年)
旧5円金貨・縮小は、直径21.82mm、8.33g、金900・銅100の硬貨であり、明治5年(1872年)に発行された金貨です。
明治3年(1870年)発行の旧5円金貨が縮小されたマイナーチェンジ版です。
⑤ 旧2円金貨(1870年)

旧2円金貨は、直径17.48mm、3.33g、金900・銅100の硬貨であり、明治3年(1870年)に発行された新貨条例による本位金貨です。
⑥ 旧2円金貨・縮小(1876年~1880年)
旧2円金貨・縮小は、直径16.97 mm、3.33g、金900・銅100の硬貨であり、明治9年(1876年)に発行された金貨です。
明治3年(1870年)発行の旧2円金貨が縮小されたマイナーチェンジ版です。
⑦ 旧1円金貨(1871年)

旧1円金貨は、直径13.51mm、1.67g、金900・銅100の硬貨であり、明治4年(1871年)に発行された新貨条例による本位金貨です。
⑧ 旧1円金貨・縮小(1874年~1880年)
旧2円金貨・縮小は、直径12.12 mm、1.67g、金900・銅100の硬貨であり、明治4年(1871年)発行の旧1円金貨が縮小されたマイナーチェンジ版です。
(2)旧銀貨
① 旭日龍1円銀貨(1870年)

旭日竜1円銀貨は、直径38.58mm、26.96g、銀900・銅100の硬貨であり、明治3年(1870年)に発行された銀貨です。
この旭日竜1円銀貨は貿易専用通貨として製造発行された硬貨であったため、当初は一般に流通することはありませんでした。
旭日竜1円銀貨は、その出来栄えの見事さから後の新1円銀貨と共に、通称「円銀」とも呼ばれており、コレクターの多い非常に人気のある高価です。
コレクターが多いがゆえに現在においては高値で取引される硬貨となっています。
もっとも、高値で取引されるがゆえに偽物も多いものですので、購入する際には注意が必要です(重さ・直系・厚さを調べるだけでなく、表面の竜図・馬の歯と言われるエッジ部分・裏面の葉っぱ部分・外周のギザギザなどの彫刻がはっきりしていなものは偽物です【本物はプレス加工がなされているために彫刻の盛り上がりがはっきりしているのですが、偽物の多くは本物の型を取ってそこに金属を流し込んで作っているため、彫刻の鋭さに差が生じます。】)。
【派生:旭日竜1円銀貨丸銀打ち】
前記のとおり、旭日竜1円銀貨は貿易専用通貨として製造発行された硬貨であったために一般流通はしていなかったのですが、明治11年(1878年)からは国内流通が認められることとなりました。
もっとも、後記のとおり、明治30年(1897年)に金本位制を採用する新しい貨幣法を制定し、あわせて1円銀貨の国内での通用を停止しました。
もっとも、この時期は、日清戦争に勝利した日本が朝鮮半島・台湾・澎湖諸島に広く進出し、これらの地域に経済圏を築いていった時期でしたので、日本のみならずこれらの周辺地域で急に1円銀貨の使用を禁止すれば大混乱に陥ることが予想されました。
そこで、一時的措置として、流通している1円銀貨について、「丸銀」という刻印を入れたものについては、外地(日本の植民地)で使用することを認めることとしたのです。
このとき行われたのが1円銀貨に対する丸銀打ちであり、具体的には、一圓の刻印の横に丸で囲んだ「銀」の文字の刻印を追加で刻んだものです。
この経過措置により混乱を鎮めようとした日本政府でしたが、実際は、丸銀打ちされたものとされていないものとが混在し、使用可能硬貨の判断が複雑となったことから、さらなる混乱を生む結果となってしまいました。
そこで、日本政府は、翌明治31年(1898年)には丸銀打ち1円銀貨の使用を取りやめるに至っています。
【派生3:旧1円銀貨・極印打ち・修正品】
貿易専用通貨として貿易用に使用された1円銀貨は、当然、海外で使用されたのですが、中国の両替商では受け取った貨幣に自社の極印(荘印)を打つことが習慣化していたため、中国に渡った時点でこの極印が刻まれる(チョップ打ちされる)こととなりました。
このように極印が刻まれた(チョップ打ちされた)1円銀貨・貿易銀を極印打ちといいます。
【派生3:旧1円銀貨・極印打ち・修正品】
もっとも、当たり前の話ですが、硬貨の表面に極印を打つとその見栄えが悪化します。
そこで、中国の両替商がチョップ打ち部分を削って塗り直すことによって銀貨の見栄えを少しでも戻そうとする行為が横行しました。
このように見栄えを戻すために手が加えられた1円銀貨・貿易銀を修正品といいます。
これらの極印打ち・修正品は現在でも多く確認されているのですが、未修正と比べて収集価値が大きく下げた評価を受けています。
② 竜1円銀貨・大型(1874年〜1887年)

明治政府によって発行された旭日竜1円銀貨は、デザインとしてはとても見事なものだったのですが、龍図の下に金額が刻印されてはいたものの、貿易専用通貨とするには手にとってすぐに金額確認が出来ないことが不便であるとの指摘があがっていました。
そこで、1円銀貨のデザインについて一面に大きく金額を刻印する方法に変えられることとなり、表面に龍、裏面に額面(額面の左側に日本政府を表す桐・右側に皇室を表す菊が刻まれています。)が刻まれるスタイルとなったのが竜1円銀貨・大型です。
竜1円銀貨・大型は、旭日竜1円銀貨はと全く同一の直径38.58mm、26.96g、銀900・銅100の硬貨であり、明治7年(1874年)に発行されました。
【派生1:貿易銀(1875年〜1877年)】

前記のとおり、貿易専用通貨として製造発行された1円銀貨でしたが、明治政府は、メキシコ銀貨が平均27.02g(417グレーン)が、平均26.96gである日本の1円銀貨よりも銀含有量が多かったことから、日本の1円銀貨の流通が阻害されていると考えました。
そこで、明治政府は、明治8年(1875年)2月28日布告により銀含有量を420グレーンに増量した貿易専用通貨を鋳造し、これを「貿易銀」とします(一圓の刻印部分から貿易銀に改められました)。
そして、明治9年(1876年)3月4日に、貿易一圓銀貨が金貨は等価と変更され、また明治11年(1878年)5月27日には貿易一圓銀貨の日本国内一般流通を認め、事実上の金銀複本位制となりました。
もっとも、量目を引き上げた貿易銀でしたが国際通貨としての地位を築くには至らず、同年11月26日に貿易専用通貨を1円銀貨に復することして貿易銀の鋳造が終了となりました。
なお、貿易銀についても丸銀打ちが存在しています。
【派生2:竜1円銀貨・大型・極印打ち】

旭日竜1円銀貨の項で記載した内容と同じです。
【派生3:竜1円銀貨・大型・極印打ち・修正品】

旭日竜1円銀貨の項で記載した内容と同じです。
【派生4・竜1円銀貨・大型・丸銀打ち】

旭日竜1円銀貨の項で記載した内容と同じです。
③ 竜1円銀貨・小型(1887年~1914年)
竜1円銀貨・小型は、直径38.1mm、26.96g、銀900・銅100の硬貨であり、明治20年(1887年)に発行されました。
それまでの竜1円銀貨と量目は同じであるものの直径が0.5mm小さくなっているために小型と呼ばれています。
なお、竜1円銀貨・小型のうち明治34年(1901年)~大正3年(1914年)発行のものは、台湾銀行兌換券の引き換え基金用に鋳造されたものであり、日本国内では流通していません。
【派生1:竜1円銀貨・小型・極印打ち】
旭日竜1円銀貨の項で記載した内容と同じです。
【派生2:竜1円銀貨・小型・極印打ち・修正品】
旭日竜1円銀貨の項で記載した内容と同じです。
【派生3・竜1円銀貨・小型・丸銀打ち】
旭日竜1円銀貨の項で記載した内容と同じです。
④ 旭日竜大型50銭銀貨(1870年~1871年)

旭日竜大型50銭銀貨は、直径32.2mm、12.50g、銀800・銅200の硬貨であり、明治3年(1870年)に発行された補助銀貨です。
⑤ 旭日竜小型50銭銀貨(1871年)
旭日竜小型50銭銀貨は、直径31mm、12.50g、銀800・銅200の硬貨であり、明治3年(1871年)に発行された銀貨です。
旭日竜大型50銭銀貨と量目は同じであるものの直径が1.2mm小さくなっているために小型と呼ばれています。
⑥ 竜50銭銀貨(1873年~1905年)

竜50銭銀貨は、直径30.9mm、13.48g、銀800・銅200の硬貨であり、明治6年(1873年)に発行された銀貨です。
竜1円銀貨と同様のデザイン上の理由から表面に竜、裏面に額面が刻まれるスタイルとなった銀貨です。
⑦ 旭日竜20銭銀貨(1870~1871年)

旭日竜20銭銀貨は、直径24mm、5.00g、銀800・銅200の硬貨であり、明治3年(1870年)に発行された補助銀貨です。
⑧ 竜20銭銀貨(1873年~1905年)

竜20銭銀貨は、直径2.350mm、5.39g、銀800・銅200の硬貨であり、明治6年(1873年)に発行された銀貨です。
竜1円銀貨と同様のデザイン上の理由から表面に竜、裏面に額面が刻まれるスタイルとなった銀貨です。
⑨ 旭日竜10銭銀貨(1870年)

旭日竜10銭銀貨は、直径17.57mm、2.50g、銀800・銅200の硬貨であり、明治3年(1870年)に発行された補助銀貨です。
⑩ 竜10銭銀貨(1873年~1906年)

竜10銭銀貨は、直径17.57mm、2.70g、銀800・銅200の硬貨であり、明治6年(1873年)に発行された銀貨です。
竜1円銀貨と同様のデザイン上の理由から表面に龍、裏面に額面が刻まれるスタイルとなった銀貨です。
⑪ 旭日竜5銭銀貨(1870~1871年)

旭日竜5銭銀貨は、直径16.15mm、1.25g、銀800・銅200の硬貨であり、明治3年(1870年)に発行された補助銀貨です。
⑫ 旭日大字5銭銀貨(1871年)

旭日大字5銭銀貨は、直径16.15mm、1.25g、銀800・銅200の硬貨であり、明治4年(1871年)に発行された銀貨です。
(3)銅貨
① 竜2銭銅貨(1873年~1884年)

竜2銭銅貨は、直径31.81mm、14.26g、銅980・錫10・亜鉛10の硬貨であり、明治6年(1873年)に発行された銅貨です。
② 竜1銭銅貨(1873年~1888年)

竜1銭銅貨は、直径27.87mm、7.13g、銅980・錫10・亜鉛10の硬貨であり、明治6年(1873年)に発行された銅貨です。
③ 半銭銅貨(1873年~1888年)

半銭銅貨は、直径22.20mm、3.56g、銅980・錫10・亜鉛10の硬貨であり、明治6年(1873年)に発行された補助銅貨です。
④ 一厘銅貨(1873年~1884年)

一厘銅貨は、直径15.75mm、0.91g、銅980・錫10・亜鉛10の硬貨であり、明治6年(1873年)に発行された補助銅貨です。
もっとも、一厘硬貨は大きさが小さい硬貨で使い勝手が悪かったために使用されないことも多く、明治時代以降も1厘硬貨の代わりとして江戸時代に使用されていた寛永通宝が補助効果として使用され続けていました(1厘=寛永通宝1文)。
そのため、1厘硬貨の発行年は明治初期の約10年間のみであり、少額硬貨でありながら発行枚数もそれ程多くありません。
なお、寛永通宝が法律上廃止されたのは、昭和28年(1953年)です。
(4)その他
① 菊5銭白銅貨(1889年~1897年)

菊5銭白銅貨は、直径20.60mm、4.67g、銅750・ニッケル250の硬貨であり、明治22年(1889年)に発行されました。
貨幣法による新貨発行(1897年)
19世紀後半になると、欧米先進国において銀価格が下落傾向にあったために銀本位制から金本位制へと移行する動きが起こります。
この動きを見た日本は、これらの国際的な経済・金融秩序に加わる目的でこれらの先進国の大勢に従うこととし、日清戦争に勝利したことにより獲得した軍事賠償金及び還付報奨金(イギリス金貨で受領)を利用して、明治30年(1897年)10月1日、新貨条例を廃止し、金本位制を基本とした金0.75g=1円とする「貨幣法」を施行します。
貨幣法では、貨幣の種類について、金貨(20円・10円・5円)、銀貨(50銭・20銭・10銭)、白銅貨(5銭)、青銅貨(1銭・5厘)の9種類と定めたため(貨幣法3条)、それまで貿易専用通貨とされていた一円銀貨の国内での通用が停止されるに至りました。
(1)新金貨(1897年〜1932年)
① 新20円金貨(1897年~1932年)

新20円金貨は、直径28.78mm、16.67g、金900・銅100の硬貨であり、明治30年(1897年)に発行された金貨です。
昭和5年(1930年)に金輸出を解除して金貨兌換を再開したのですが、翌昭和6年(1931年)に円相場が下落したため、その多くが海外に流出して地金されています。
その結果、同年12月に金が輸出禁止とされ、紙幣による金貨への兌換も停止されています。
② 新10円金貨(1897年~1910年)

新10円金貨は、直径21.21mm、8.33g、金900・銅100の硬貨であり、明治30年(1897年)に発行された金貨です。
③ 新5円金貨(1897年~1930年)

新5円金貨は、直径16.96mm、4.17g、金900・銅100の硬貨であり、明治30年(1897年)に発行された金貨です。
(2)新銀貨
① 旭日50銭銀貨(1906年~1917年)

旭日50銭銀貨は、直径27.27mm、10.13g、銀800・銅200の硬貨であり、明治39年(1906年)に発行された銀貨です。
② 八咫烏50銭銀貨(1918年~1919年)

八咫烏50銭銀貨は、直径24.85mm、6.75g、銀800・銅200の硬貨であり、大正7年(1918年)に発行される予定であった銀貨です。
鋳造されて日銀に引き渡されたのですが、この時期に銀価格が急騰したために流通に供されることはなく回収されてしまっています。
③ 鳳凰50銭銀貨(1922年~1938年)

鳳凰50銭銀貨は、直径23.50mm、4.95g、銀720・銅280の硬貨であり、大正11年(1922年)に発行された銀貨です。
前記のとおり、大正7年(1918年)頃に起こった銀価格の高騰を受け、八咫烏50銭銀貨から銀含有量を大きく低下させた銀貨となっています。
鳳凰50銭銀貨は、八咫烏50銭銀貨から銀含有量を大きく低下してサイズダウンしていることから、小型50銭銀貨とも呼ばれています。
④ 旭日20銭銀貨(1906年~1911年)

旭日20銭銀貨は、直径20.30mm、4.05g、銀800・銅200の硬貨であり、明治39年(1906年)に発行された銀貨です。
⑤ 旭日10銭銀貨(1907年~1917年)

旭日10銭銀貨は、直径17.57mm、2.25g、銀800・銅200の硬貨であり、明治40年(1907年)に発行された銀貨です。
⑥ 八咫烏10銭銀貨(1918年~1919年)

八咫烏10銭銀貨は、直径16.06mm、1.50g、銀800・銅200の硬貨であり、大正7年(1918年)に発行される予定であった銀貨です。
鋳造されて日銀に引き渡されたのですが、この時期に銀価格が急騰したために流通に供されることはなく回収されてしまっています。
(3)銅貨
① 稲5銭白銅貨(1897年~1905年)

稲5銭白銅貨は、直径20.60mm、4.67g、銅750・ニッケル250の硬貨であり、明治30年(1897年)に発行されました。
② 大型5銭白銅貨(1917年~1920年)

大型5銭白銅貨は、直径20.60mm、4.28g、銅750・ニッケル250の硬貨であり、大正6年(1917年)に発行されました。
③ 稲1銭白銅貨(1898年~1915年)

稲1銭青銅貨は、直径27.87mm、7.13g、銅950・錫40・亜鉛10の硬貨であり、明治31年(1898年)に発行されました。
④ 桐1銭青銅貨(1916年~1938年)

桐1銭青銅貨は、直径23.03mm、3.75g、銅950・錫40・亜鉛10の硬貨であり、大正5年(1916年)に発行されました。
⑤ 5厘青銅貨(1916年~1919年)

5厘青銅貨は、直径18.78mm、2.10g、銅950・錫40・亜鉛10の硬貨であり、大正5年(1916年)に発行されました。
銀価格高騰による硬貨変更(1920年)
第一次世界大戦時に欧米諸国が金の輸出を停止したことに倣って、日本でも金本位制を停止し、金貨の製造を休止します。
そして、これら主要国が金貨の製造を休止したことにより各国高額貨幣の中心が銀貨に移行したのですが、この結果、世界的な銀不足に陥り、世界規模で銀価格が急騰します。
その後、昭和4年(1929年)にアメリカの株価暴落で始まり全世界に波及した世界恐慌のあおりを受け、日本では昭和5年(1930年)に金輸出を解除して金貨の兌換を再開したのですが不況の流れを断ち切ることが出来ず、昭和6年(1931年)に円相場もまた急落します。
この結果、日本発行金貨が大量に海外流出する事態に発展したため、同年12月金の輸出禁止と紙幣による金貨への兌換禁止とされ、金本位制を完全停止することにより管理通貨制へ移行されました(日本における金貨発行が終了)。なお、日本のみならず全世界で金本位制からの脱却が行われています。
(1)10銭白銅貨(1920年~1932年)

前記のとおり、大正7年(1918年)頃に世界的な銀価格の高騰があり、既に鋳造済みであった八咫烏銀貨が鋳潰点を上回ったために流通しないこととなりました。
他方、10銭硬貨を高騰する銀価格に合わせたものとすると、余りに小さな効果となってしまい流通上不便となると判断されました。
そこで、大正9年(1920年)に貨幣法を改正して10銭銀貨が削除され、代わって10銭白銅貨が加えられることとなりました。
この結果として発行されたのが10銭白銅貨です。
10銭白銅貨は、直径22.17mm、3.75g、銅750・ニッケル250の硬貨であり、大正9年(1920年)に発行されました。なお、銀価格の高騰を受けて10銭硬貨が銀貨ではなくなったのに対し、50銭については八咫烏50銭銀貨から銀含有量を大きく低下させた鳳凰五十銭銀貨に変更はされつつ銀貨であることは維持されています。
(2)小型5銭白銅貨(1920年~1932年)

小型5銭白銅貨は、直径19.09mm、2.63g、銅750・ニッケル250の硬貨であり、大正9年(1920年)に発行されました。
大型5銭白銅貨が10銭白銅貨と同様図案の有孔貨幣であったことから間違えやすかったため、バランスをとるために大型5銭白銅貨を縮小する形で発行されたマイナーチェンジ版です。
小額政府紙幣を回収する目的から大量に発行された硬貨でもあります。
(3)5銭ニッケル貨(1933年~1937年)

5銭ニッケル貨は、直径19mm、2.80g、ニッケル1000の硬貨であり、昭和8年(1933年)に発行されました。
ニッケル逼迫による硬貨変更(1938年)
昭和12年(1937年)に日中戦争が勃発したことにより、軍需用金属(ニッケル・銅など)の需要が増大したのですが、その多くを輸入に頼っていた日本では、これらの金属を硬貨に使用する余裕がなくなります。
日中戦争の拡大による金属不足により貨幣法で定めた金貨・銀貨・白銅貨・青銅貨の鋳造が困難となったため、昭和13年(1938年)6月1日に「臨時通貨法」を施行して、日本国内で豊富に産出されるなどの調達の容易な金属で代替した「臨時補助貨幣」が製造されることとなりました。なお、臨時通貨法は、日中戦争終戦後1年までの時限立法として施行されたのですが、昭和17年(1942年)2月に太平洋戦争終戦後1年まで期限を延長された後、昭和21年(1946年)に期限を規定していた附則第二項が削除されることで期限の定めがなくなっています。
臨時通貨法の制定により貨幣法を改正することなく貨幣法規定「貨幣」以外の「臨時補助貨幣」を発行することが可能となり、以降、貨幣法の規定が有名無実化して戦時下における貨幣用資材調達の都合に合わせて様々な素材・品位・量目の臨時補助貨幣が発行されるようになります。
まず、日中戦争の戦線拡大により、鉄に混ぜると粘り強く・錆びにくく・耐熱性を持つステンレス鋼を構成するニッケルの需要がひっ迫していったため、昭和13年(1938年)にそれまでの10銭・5銭ニッケル硬貨が廃止され、10銭・5銭硬貨ではアルミニウム青銅(銅+アルミ)が、1銭硬貨では黄銅(銅+亜鉛)が使用されることとなりました。
また、このときに50銭銀貨の発行が中止された上、さらには市中に出回っている銀を回収するために五十銭紙幣(富士桜50銭紙幣)を発行して銀貨との交換が進められました。なお、このとき発行された紙幣は、小額紙幣整理法の制定により、昭和23年(1948年)8月31日に通用禁止とされています。
(1)10銭アルミ青銅貨(1938年~1940年)
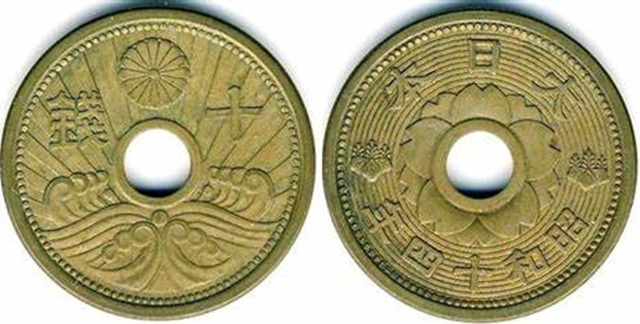
10銭アルミ青銅貨は、直径22mm、4.00g、銅950・アルミ50の硬貨であり、昭和13年(1938年)に発行されました。
(2)5銭アルミ青銅貨(1938年~1940年)

5銭アルミ青銅貨は、直径19mm、2.80g、銅950・アルミ50の硬貨であり、昭和13年(1938年)に発行されました。
(3)カラス1銭黄銅貨(1938年)

カラス1銭黄銅貨は、直径23.03m、3.75g、銅900・亜鉛100の硬貨であり、昭和13年(1938年)に発行されました。
(4)カラス1銭アルミ貨(1938年~1940年)

カラス1銭アルミは、直径17.60m、0.90g、アルミ1000の硬貨であり、昭和13年(1938年)に発行されました。
ニッケル硬貨を廃止して青銅貨・黄銅貨を使用し始めたのですが、銅の調達自体も順調ではなかったため、安価な1銭硬貨においては銅の使用すら取りやめ、昭和13年(1938年)11月、発行して間もない1銭黄銅貨がアルミ貨に変更されました。
銅逼迫によるアルミ貨発行(1940年〜)
泥沼の消耗戦へと突入した日中戦争の長期化が、英米を始めとする欧米諸国の不信を招き、日本と欧米諸国との対立に繋がっていきました。
その結果、昭和15年(1940年)7月、アメリカが石油・屑鉄・鋼などの対日輸出制限を開始し、同年8月にはガソリン、同年9月には屑鉄の対日輸出禁止を行います(平成16年/1941年8月には石油の対日禁輸がなされました。)。
以上の結果、日中戦争を維持するために必要な金属・エネルギー全般が滞るようになり、日本国内での銅鉱山の拡充や旧鉱山の復活が進められると共に、これらを優先的に軍需品製造に充てる努力が進められ、昭和16年(1941年)に金属回収令が制定されて日本国内での金属回収やエネルギー節約が進められていくようになりました。
この一環として、硬貨の変更も行われ、それまでの硬貨で使用されていた銅が取り除かれ、この時点では比較的利用しやすかったアルミニウム硬貨となりました。
(1)菊10銭アルミ貨(1940年~)

菊10銭アルミ貨は、直径22mm、1.50g、アルミ1000の硬貨であり、昭和15年(1940年)に発行されました。
もっとも、第二次世界大戦の戦局悪化によりアルミニウムの調達も難しくなっていき、昭和16年(1941年)には量目が1.20gに、また昭和18年(1943年)には量目が1.00gにそれぞれ縮小されています。
(2)5銭アルミ貨(1940年~)

5銭アルミ貨は、直径19mm、1.20g、アルミ1000の硬貨であり、昭和15年(1940年)に発行されました。
もっとも、第二次世界大戦の戦局悪化によりアルミニウムの調達も難しくなっていき、昭和16年(1941年)には量目が1.00gに、また昭和18年(1943年)には量目が0.80gにそれぞれ縮小されています。
(3)富士1銭アルミ貨(1941年~)

富士1銭アルミ貨は、直径16mm、0.65g、アルミ1000の硬貨であり、昭和16年(1941年)に発行されました。
もっとも、第二次世界大戦の戦局悪化によりアルミニウムの調達も難しくなっていき、昭和18年(1943年)に量目が1.00gに、また昭和18年(1943年)には量目が0.55gに縮小されています。
戦局悪化による錫貨や金属以外硬貨の発行
もっとも、昭和17年(1942年)6月に起こったミッドウェー海戦に敗れて太平洋一帯の制海権を失った日本では、さらに兵站ルートが制限されることとなった結果、航空機の機体材料となるアルミニウムの調達もままならなくなったことからアルミ貨の鋳造も困難となり、そればかりかアルミニウムもまた金属回収令の対象に加えられました。
そこで、硬貨の材料として選択されたのが、当時日本の勢力下にあった東南アジア各地域で豊富に生産される「錫」でした。
錫は熱に弱い上にやわらかいため、本来は貨幣として適切な材料とは言えないのですが、使用すべきではない素材です、他に選択肢のなかった時代の苦渋の決断による硬貨発行だったのです。
(1)10銭錫貨(1944年)

10銭錫貨は、直径19mm、2.40g、錫930・亜鉛70の硬貨であり、昭和19年(1944年)に発行されました。
(2)穴アキ5銭錫貨(1944年)

穴アキ5銭錫貨は、直径17mm、1.95g、錫930・亜鉛70の硬貨であり、昭和19年(1944年)に発行されました。
(3)1銭錫貨(1944年~1945年)

1銭錫貨は、直径17mm、15g、錫500・亜鉛500の硬貨であり、昭和19年(1944年)に発行されました。
(4)その他の試鋳硬貨(陶貨等)
また、第二次世界大戦末期には、物資不足から錫貨の他にも、金属以外の素材を利用した硬貨が検討されました。
その中でも特に特殊なものものとしてよく例に挙げられるのが陶貨です。
物資不足への対策から昭和19年(1944年)ころから粘土と長石を主原料とする陶器硬貨の採用が検討され、昭和20年(1945年)ころから意匠の決定や衝撃・落下実験が繰り返されました。
そして、同年4月からは民間委託の方法により、京都市所在の松風工業で10銭陶貨、愛知県所在の瀬戸輸出陶器株式会社で5銭陶貨、佐賀県有田町所在の協和新興陶器有限会社と前記2つの工場とで1銭陶貨が製造され、その合計枚数は約1500万枚にも及んだのですが、実際に使用されることはなく終戦時にそのほとんどが粉砕処分とされました。
また、当時日本の植民地であった満州では、マグナサイトを焼成したマグネサイト貨という天然石を加工した脆い貨幣が発行されました。
戦後の硬貨改鋳(1945年)
第二次世界大戦に敗れて産業が壊滅的打撃を受けて農産物・工業製品が不足する中、多くの軍人等が国内に引き上げてきた上、これらの者に一斉に退職金の支払いがなされたことにより物不足・過剰現金発行による猛烈なインフレが進みました(東京の小売物価は、昭和21年が前年比6倍、昭和22年が前年比2.7倍、昭和23年が前年比3倍など)。
こうなると、それまでの貨幣制度では混乱を収束できなくなります。
そこで、日本政府は、昭和21年(1946年)2月末までに旧紙幣を金融機関に預け入れすることを強制し、翌月から毎月世帯主は300円・家族は100円の限度で引き出せることとします。
その上で、それまでの有名無実化した貨幣法と臨時通貨法により臨時補助貨幣の発行がなされました。
この際、それまで軍事用に回されていた砲弾や薬莢などを構成する金属が硬貨の材料とされています。
(1)1円黄銅貨(1948年~1950年)

1円黄銅貨は、直径20mm、3.20g、銅600~700・亜鉛400~300の硬貨であり、昭和23年(1948年)に発行されました。
(2)大型50銭黄銅貨(1946年~1947年)

大型50銭黄銅貨は、直径23.50mm、4.50g、銅600~700・亜鉛400~300の硬貨であり、昭和21年(1946年)に発行されました。
(3)小型50銭黄銅貨(1947年~1948年)

小型50銭黄銅貨は、直径19mm、2.80g、銅600~700・亜鉛400~300の硬貨であり、昭和22年(1947年)に発行されました。
(4)稲10銭アルミ貨(1945年~1946年)

稲10銭アルミ貨は、直径22mm、1.00g、アルミ1000の硬貨であり、昭和20年(1945年)に発行されました。
戦中は、材料不足から錫を材料としていた10銭硬貨(5銭・1銭も同様)でしたが、戦後になって軍事利用が不要となったため、10銭硬貨については硬貨の材料として相応しくない錫貨は取りやめられ、造幣局のわずかな手持ち資材のアルミニウムを使用してアルミ貨として発行されることとなりました。
もっとも、終戦直後はGHQによりアルミニウムの生産が禁止されていたためにすぐに資材が枯渇し、発行翌年の昭和21年(1946年)に発行が中止されています。
なお、この稲10銭アルミ貨が日本最後の10銭硬貨となっています。
(5)鳩5銭錫貨(1945年~1946年)

鳩5銭錫貨は、直径17mm、2.00g、錫930・亜鉛70の錫貨であり、昭和20年(1945年)に発行された硬貨です。
前記のとおり、錫は硬貨の材料としては適切ではなかったものの、額面5銭の硬貨でアルミを材料としてしまうと素材価格が額面を上回ってしまうため採用することができず、戦中同様に錫貨として発行されました。
戦後に発行された硬貨に相応しく、その図柄に平和の象徴である鳩が刻まれています。
現行硬貨の歴史と各硬貨の説明
戦後に行われた市場に出回る貨幣量の制限政策(新円切り替え)は、インフレを完全に食い止めることはできず、貨幣価値がどんどん低下していきまきた。
そのため、インフレ化する物価に合わせた高額通貨発行の必要に迫られ、それまでの臨時通貨法に従って新たな1円硬貨・5円硬貨(その後、10円・50円・100円)が発行されていきました。
そして、終戦後の物価上昇により1円未満の硬貨が使用されることがほぼなくなったため、昭和28年(1953年)に小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(小額通貨整理法)が制定され、同年12月31日限りでそれまで発行されていた1円未満の貨幣の通用力が失われました。
その後、昭和63年(1988年)に通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律が施行されると共に500円硬貨の発行がなされて、現行硬貨の通貨単位が「五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類」と定められて現在の額面系列となるに至っています。
500円硬貨
(1)500円白銅貨(1982年~1999年)

戦後、1円・5円・10円・50円・100円硬貨が発行され、これ以上の額面は紙幣で運用されていたのですが、経済成長によるインフレと貨幣の安全性を高める観点から500円については紙幣から硬貨に変更しようという声が上がり始めます。
そこで、昭和56年(1981年)5月15日、臨時通貨法の改正が行われて500円貨種が追加され、昭和57年(1982年)4月1日から臨時補助貨幣として直径26.5mm、7.20g、銅750・ニッケル250の500円白銅貨が発行されるに至りました
そして、昭和63年(1988年)に通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律が施行されると500円硬貨も通貨とみなされました。
なお、500円白銅貨発行後も暫くの間は500円紙幣も並行して発行・使用されていたのですが、平成6年(1994年)に日本銀行からの支払が停止されたことにより500円紙幣が500円硬貨に完全に置き換えられるに至っています。
なお、余談ですが、日本の500円硬貨は、スイスの5フラン硬貨に次ぐ世界2位の高額高架となっています。
(2)500円ニッケル黄銅貨(2000年~2021年)

500円ニッケル黄銅貨は、直径26.5mm、7.00g、銅720・亜鉛200・ニッケル80の硬貨であり、平成12年(2000年)に発行されました。
同年に硬貨の材質・デザインが変更された理由は、それまでの500円白銅貨が韓国の500ウォン硬貨と似ていたために自動販売機で500ウォン硬貨を500円硬貨と誤認してしまう問題が頻発していたため、これらを区別する目的で行われました。
(3)新500円バイカラー・クラッド貨幣(2021年~)

新500円バイカラー・クラッド貨幣は、直径26.5mm、7.10g、銅750・亜鉛125・ニッケル125の硬貨であり、令和3年(2024年)に発行されました。
100円硬貨
(1)鳳凰100円銀貨(1957年〜1958年)

鳳凰100円銀貨は、直径22.6mm、4.80g、銀600・銅300・亜鉛100の硬貨であり、昭和32年(1957年)に発行されました。
量目が、4.80gであり、そのうち60%が銀ですので、この硬貨には2.88gの銀が含まれていることになります。
そのため、額面どおり現在も100円として使用できる硬貨なのですが、今日では電子部品などの工業用需要の増大により鉱物としての銀の価格が上昇しているため、鉱物価格が額面を上回る状況となっています。
もっとも、法律上、法定貨幣を損傷したり鋳潰したりすることが禁止されており、違反した場合には1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられるとされていますので(貨幣損傷等取締法)、くれぐれも精錬して銀を取り出す行為は控えて下さい。
(2)稲100円銀貨(1959年〜1966年)

稲100円銀貨は、直径22.6mm、4.80g、銀600・銅300・亜鉛100の硬貨であり、昭和34年(1959年)に発行されました。
一般流通用としての最後の銀貨です。
法律上、損傷や鋳潰しが禁止されていることは鳳凰100円銀貨と同様です。
(3)桜100円白銅貨(1967年〜)

桜100円白銅貨は、直径22.6mm、4.80g、銅750・ニッケル250の硬貨であり、昭和42年(1967年)に発行されました。
工業製品での利用などにより世界的に銀の需要が増大したことから、世界的に銀貨を廃止して他の素材へ変更する流れが生まれ、この流れに従って日本でも銀貨が廃止されることとなったことにより生まれた硬貨です。
なお、余談ですが、鳳凰100円銀貨と稲100円銀貨は銀貨であり、桜100円白銅貨であることから比重が異なります(銅よりも銀の方が重たいはずです)。
それにも関わらず、これらの3つの硬貨はいずれも直径22.6mmという同じ大きさになっています。
不思議に思われる方がおられるかも知れませんが、この点については硬貨の厚みを変えることで同じ大きさを実現しています(桜100円白銅貨は、鳳凰100円銀貨と稲100円銀貨よりも厚くなっています)。
50円硬貨
(1)菊穴ナシ50円ニッケル貨(1955年~1958年)

菊穴ナシ50円ニッケル貨は、直径25.0mm、5.50g、ニッケル1000の硬貨であり、昭和30年(1955年)に発行されました。
50円硬貨が発行される前は、高額面(1000円・500円・100円・50円)は紙幣で発行されていたのですが、このとき、このうちの最低額の50円が紙幣から硬貨に切り替えられました。
(2)菊50円ニッケル貨(1959年~1966年)

菊50円ニッケル貨は、直径25.0mm、5.00g、ニッケル1000の硬貨であり、昭和34年(1959年)に発行されました。
発行枚数が少ない昭和35年(1960年)が特年、続けて少ない昭和34年(1959年)・昭和36年(1961年)が小特年とされています。
(3)50円白銅貨(1967年~)

50円白銅貨は、直径21.0mm、4.00g、銅750・ニッケル250の硬貨であり、昭和42年(1967年)に発行されました。
10円硬貨
10円硬貨については、昭和25年(1950年)に直径20.0mm、2.79g、ニッケル160〜180・銅550〜600・亜鉛220〜290の穴アキ洋銀貨として発行する準備が進められ、同年と翌昭和26年(1951年)に鋳造され始めたのですが、朝鮮戦争勃発によりニッケル相場が高騰したため、ニッケルを含む10円硬貨の発行が急遽取りやめられることとなりました。
そこで、新たにニッケルを含まない銅貨の10円硬貨に切り替えられることとなりました。
(1)10円青銅貨・ギザあり(1953年〜1958年)

10円青銅貨(ギザあり)は、直径23.5mm、4.50g、銅950・亜鉛40・錫10の硬貨であり、昭和26年(1951年)に発行されました。
なお、より正確に言えば、鋳造されたのは昭和26年(1951年)からであり、翌昭和27年(1952年)も鋳造はされたのですが、この2年の間は発行して市中に流通しておらず、市中に出回ったのは昭和28年(1953年)です。そのため、発行年は昭和28年(1953年)というのが正確かも知れません。
硬貨の周囲にギザギザが刻まれていることから、通称「ギザ10」と呼ばれています。
周囲にギザギザが刻まれる硬貨は、一般的にはその国の高額硬貨として認識されている硬貨であり、手に持った際に他の低額硬貨と区別しやすくするための工夫です。
では、なぜ10円硬貨のような安価とも思える硬貨にギザギザが刻まれていたかというと、10円硬貨(10円青銅貨・ギザあり)が発行された昭和26年(1951年)の時点ではこれ以上の額面の硬貨が存在しておらず、日本最高額の硬貨だったからです。
(2)10円青銅貨・ギザなし(1959年〜)

10円青銅貨(ギザなし)は、直径23.5mm、4.50g、銅950・亜鉛40・錫10の硬貨であり、昭和34年(1959年)に発行されました。
昭和30年(1955年)に50円硬貨が、昭和32年(1957年)に100円硬貨がそれぞれ発行され、10円硬貨が高額硬貨と言えなくなったこともあって、昭和34年(1959年)以降発行の10円硬貨には、周囲のギザギザがなくなり、周囲がツルツルの効果として発行されるようになりました。
5円硬貨
(1)穴ナシ5円黄銅貨(1948年〜1949年)

穴ナシ5円黄銅貨は、直径22mm、4.00g、銅600 〜700・亜鉛400 〜300の硬貨であり、昭和23年(1948年)に発行されました。
(2)5円黄銅貨・楷書体(1949年〜1958年)
.jpg)
5円黄銅貨・楷書体は、直径22mm、3.75g、銅600 〜700・亜鉛400 〜300の硬貨であり、昭和24年(1949年)に発行されました。
硬貨に刻まれた文字が楷書体(筆書き様)となっていることから、通称「フデ5」と呼ばれています。国名が日本國と旧字体で刻まれていることも特徴です。
なお、現行硬貨の中でこの5円黄銅貨のみ裏面(年号が刻まれている側)に金額を示す数字が入っていないのが特徴的です。
(3)5円黄銅貨・ゴシック体(1959年〜)

5円黄銅貨・ゴシック体は、直径22mm、3.75g、銅600 〜700・亜鉛400 〜300の硬貨であり、昭和34年(1959年)に発行されました。
1円硬貨
(1)1円アルミ貨(1955年~)

1円アルミ貨は、直径20mm、1.00g、アルミ1000の硬貨であり、昭和30年(1955年)に発行されました。
.jpg)