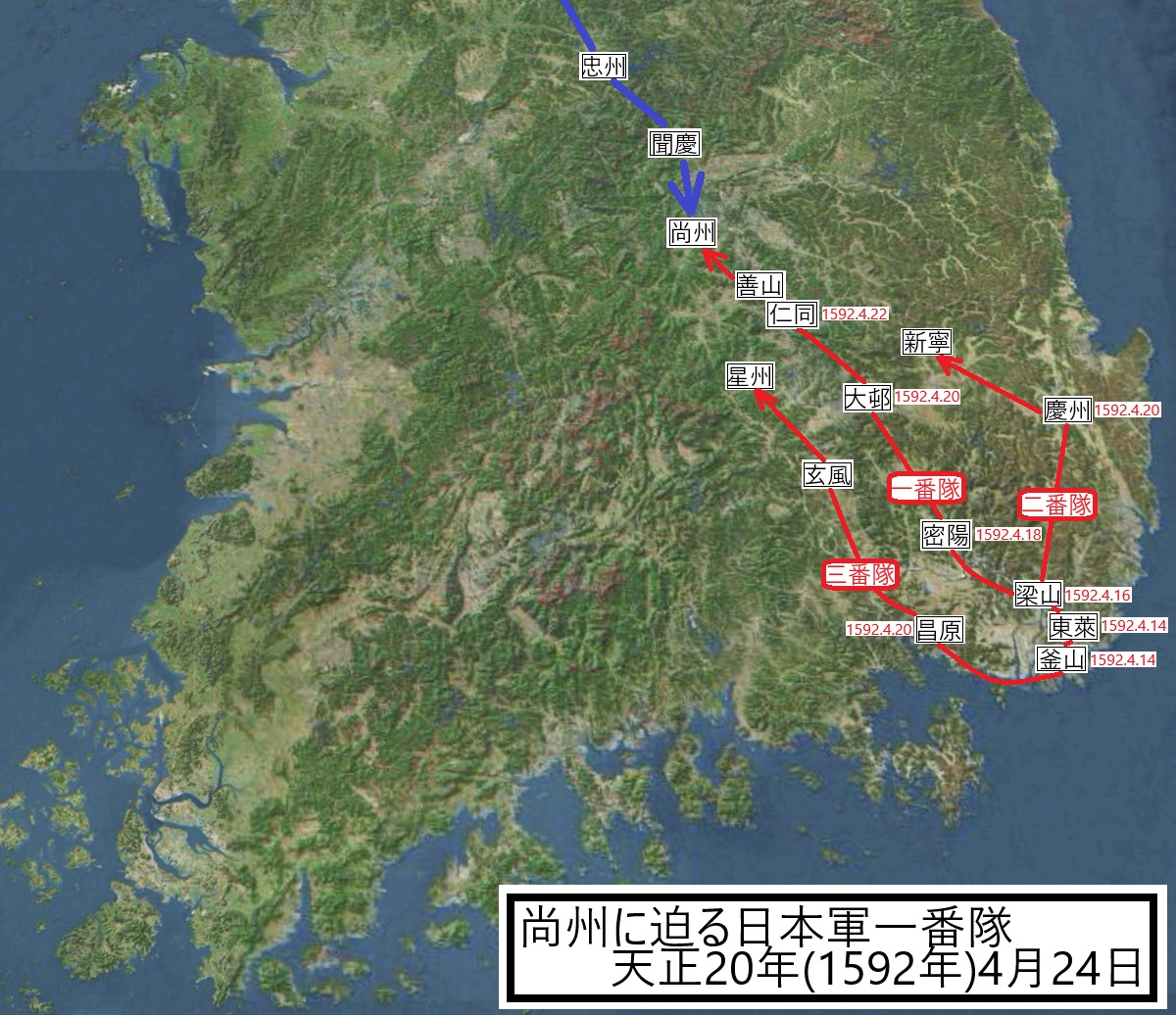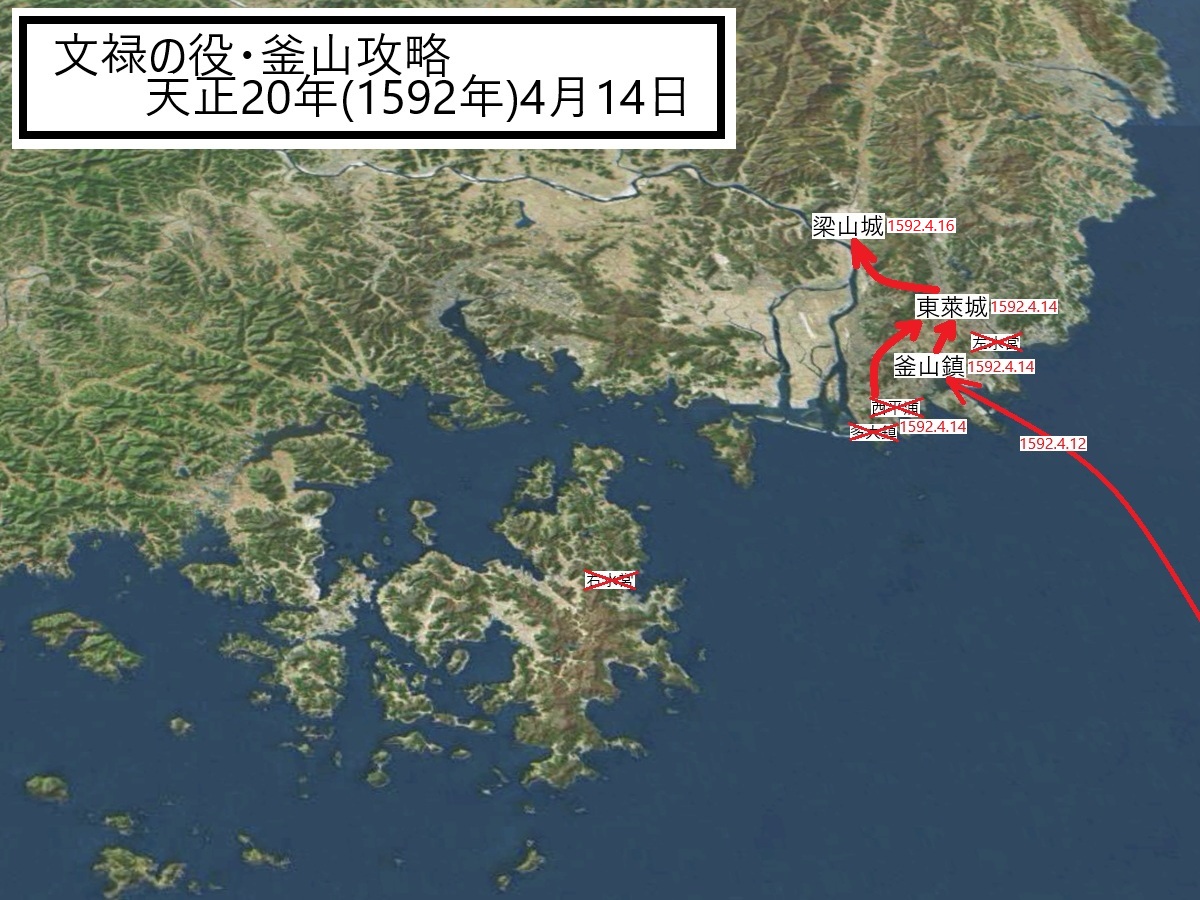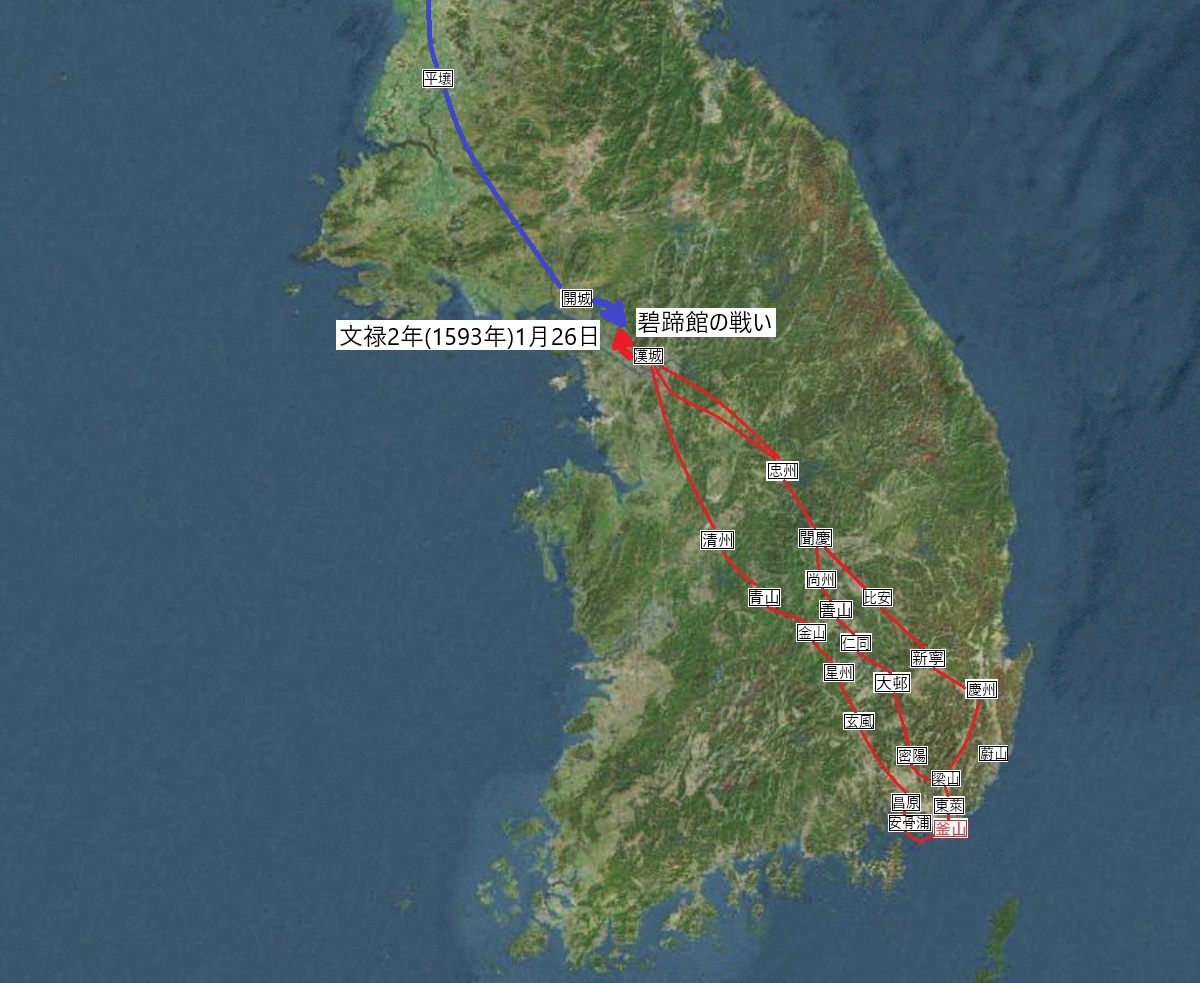第二次晋州城の戦いは、文禄の役の際に朝鮮方に与して明国が参戦したことにより苦しくなった日本軍が釜山にまで戦線を下げるに至ったのですが、そこで兵站に余裕ができたために全羅道制圧をするために大軍を編成して同城を攻めた戦いです。
攻められることとなった朝鮮軍では、宗主国でもある明国に援軍を要請したのですが、日明間で講和交渉を行っていた明国がこの援軍要請を拒否したため、日本軍対朝鮮軍との戦いとなりました。
文禄2年(1593年)6月21日に9万人を超える大軍で晋州城に取りついて攻撃を開始した日本軍が、1週間かけて同城を攻略したという文禄の役最大規模の戦いであり、勝利した日本軍が同城に籠った朝鮮軍を根切りにした殺戮戦でもありました。 “【第二次晋州城の戦い】文禄の役最大の攻城戦” の続きを読む
.jpg)
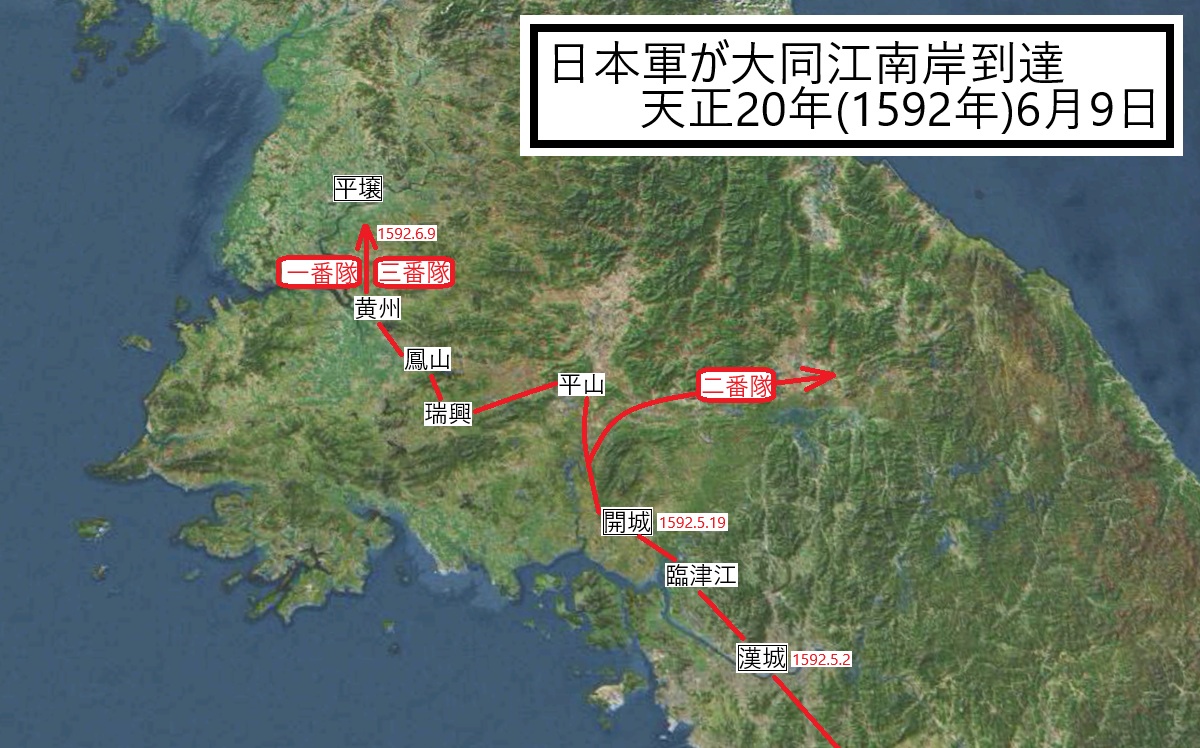
.jpg)