日本全国統一戦を進めていた織田信長が明智光秀の謀反によって横死した本能寺の変は、その後の中国大返しと山崎の戦いの勝利によって羽柴秀吉が天下人の階段を駆け上がっていくきっかけとなった歴史を変える一大事件でした。
もっとも、本能寺の変が起こった際、羽柴秀吉は毛利家の城であった備中高松城の水攻めを行っている最中であり、本能寺の変の詳細を知るべき状況下にはなかったはずです。
このような状況下において運命を手繰り寄せた羽柴秀吉は、どのようにして本能寺の変発生の事実を正確に獲得したのでしょうか。
本稿では、羽柴秀吉が本能寺の変発生を知るに至った経緯について説明していきたいと思います。 “羽柴秀吉は本能寺の変をいつ・どうやって知ったのか” の続きを読む
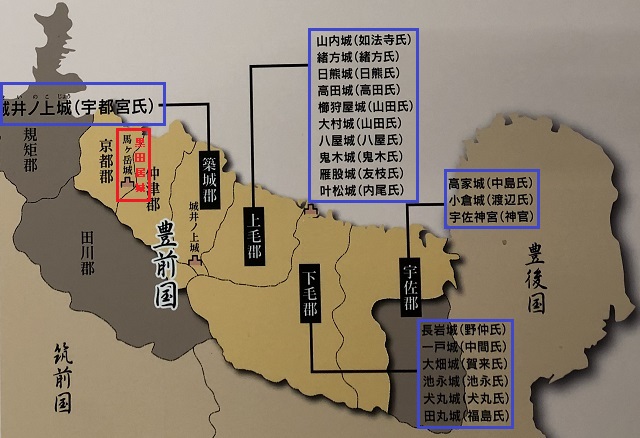
.jpg)


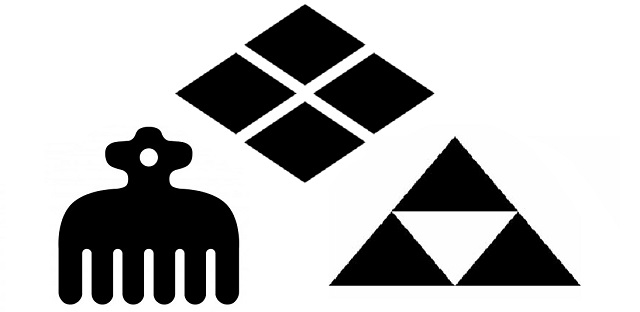
.jpg)

