恭仁京(くにきょう/くにのみやこ)は、奈良時代の天平12年(740年)から僅かの間だけ山背国相楽郡(現在の京都府木津川市加茂地区)に置かれた日本の都です。
正式名称は、「大養徳恭仁大宮(やまとのくにのおおみや)」といいます。
恭仁京は、天然痘流行や藤原博嗣の乱により平城京が穢れたと考えた聖武天皇が、霊力を取り戻すためにかつて壬申の乱の際に天武天皇が辿ったルートを行幸し、そこで得た霊力を基に仏教を基にした新たな時代を造ろうとした野心的な都でした。
もっとも、恭仁京遷都後も、難波宮や紫香楽宮(甲賀宮)への遷都を試みるなどして人臣の信頼を失い、最終的には平城京に戻されることで遷都計画が失敗に終わりました。なお、この間の聖武天皇の動きは、彷徨五年と呼ばれ、複数回の遷都の理由についても謎が多い面白い行動でもあります。
本稿では、聖武天皇の発案により遷都された恭仁京(またそのうちの恭仁宮)について、遷都に至る経緯から順に説明していきたいと思います。 “【恭仁京】奈良時代に数年間だけ存在した山背国の都” の続きを読む

.jpg)

.jpg)
.jpg)
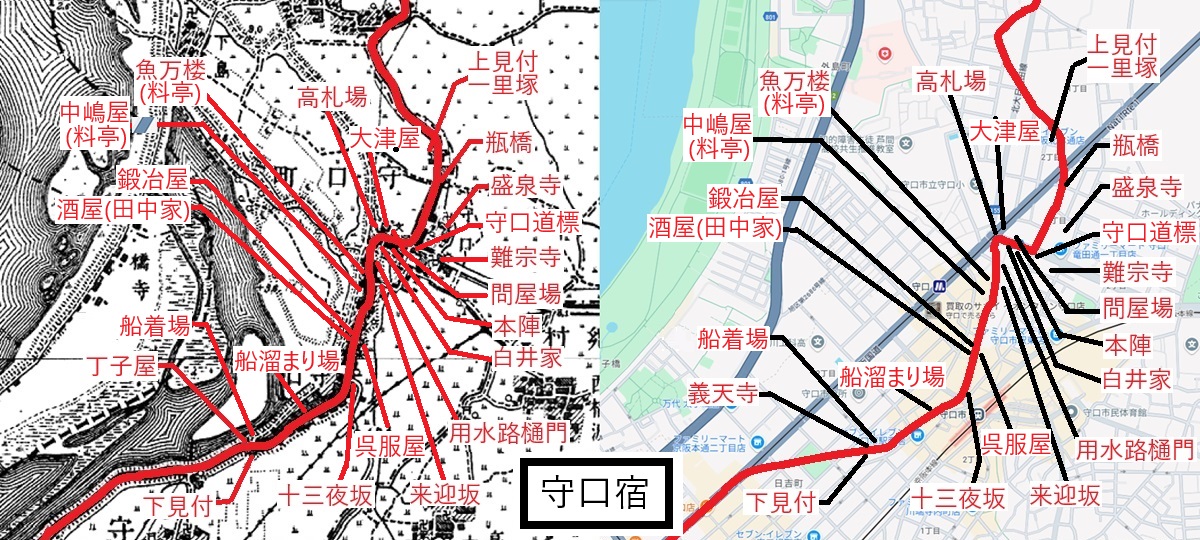
.jpg)
.jpg)